コールセンターのKPI(重要業績評価指標)とは?
更新日:2024.06.21コールセンターコールセンターのKPIは、各種業務の成果を測定するための指標です。基本的に、着信時の応答や通話が速やかに進められているか評価する基準として設定されます。主なKPIについて理解を深めれば、コールセンターで業績評価の指標を設ける時に役立つでしょう。そこで今回は、コールセンターでKPIが設定される理由をふまえ、代表的な関連用語などをご紹介します。
電話代行サービス満足度No.1
月50件からOK!98%以上の高い応答率のコールセンター代行サービスの詳細はこちら
目次
なぜコールセンターで「KPI」が設定されるのか
KPIは、様々な業績を評価する指標です。通常、企業の目標を達成するうえで重要な業務について、仕事の進捗状況や成果を測る指標が設定されます。以下では、コールセンターにおける具体的な指標やKPIの設定が必要になる理由をご紹介します。
コールセンターの「KPI」とは?
コールセンターで設定されるKPIは、応答率や平均応答時間をはじめ多種多様です。多くのコールセンターは、お客様や取引先に喜ばれるため迅速かつ的確な電話対応を目標に掲げています。お客様や取引先から電話があった時は、素早く着信対応するとともに丁寧に話を聞き、電話の用件をスムーズに処理することを目指しています。
いくつもの目標を達成する必要から、コールセンターでは、多岐にわたるKPIを設定するケースが一般的です。具体的なKPIは多く知られますが、大きく応答品質・生産性および収益性・顧客満足度・従業員マネジメントの4つに分けられます。コールセンターは、これら4項目について業績を評価するための指標を設け、適切な電話対応によるサービスの向上に努めています。
コールセンターでKPIが設定される理由
コールセンターでKPIが設定される理由は、お客様や取引先に喜ばれる電話対応を実現するためです。この目標を達成するうえでは、応対品質・効率性・顧客満足度・マネジメントなどの改善が必要になります。ただし、具体的な評価基準がなければ、どれくらい改善できたか確認するのは困難です。
電話の応対品質や効率性の改善状況は、それぞれの業務の評価基準を設定することで把握しやすくなります。応答率や応答時間の指標を数値で示せば、目に見える形での評価が可能です。そのため、コールセンターでは、様々な業務改善の達成状況を測定する方法として、指標となるKPIを設定しています。
コールセンターのKPIに関連する用語
コールセンターのKPIは数々あり、関連する用語は多彩です。難解な用語も少なくないため、以下ではKPIの代表的な関連用語について解説いたします。
目標達成度を評価する指標
様々な目標の達成度を評価する指標は、基本的にKGIとKPIの2つです。また、全体的な目標と個々の指標を組み合わせる方式として、OKRがあります。
KGI
KGIは、企業にとっての最終的な目標です。この用語はKey Goal Indicatorの略であり、「重要目標達成指標」と和訳されます。どの業種でも、それぞれの企業では、社内全体で目指す経営目標を設定しているでしょう。各企業で最終目標の達成度を測定するために設定する指標が、KGIに該当します。コールセンターの場合、お客様や取引先に満足される電話対応の実現が、最終的な企業目標になると考えられます。
KPI
KPIは、最終目標を達成するうえで重要になる個別の業務目標です。Key Performance Indicatorsの略称であり、「重要業績評価指標」とも呼ばれています。企業の最終目標は、様々な業務が成果を上げることで達成されるものと考えられます。各々の業務目標は最終的なゴールへ到達する過程段階にあるため、中間目標に位置づけられるケースが一般的です。コールセンターでは、電話のつながりやすさやスムーズな受け答えを中間目標に設定するケースが多く見られます。
OKR
OKRは、Objective and Key Resultの略です。それぞれ、「目標」と「主要な結果(成果指標)」を意味します。この方式の大きな特徴は、従業員の能力向上が企業全体の業績アップにつながるように全体的な目標と各業務の成果指標を設定できるところです。そのため、企業全体と従業員個人の目標・指標を結びつけられるメリットがあります。個人のスキルアップが企業の業績拡大につながりやすい特徴から、最近はコールセンターに限らず多くの業種で注目を集めています。
※関連記事「目標管理制度(MBO)の特徴や注意点とは」はこちら
応答品質に関する指標
コールセンターが電話の応答品質を高める時に重視している指標は、着信時の応答率(放棄呼率)やSL(サービスレベル)です。
応答率(放棄呼率)
応答率は、着信時に応答できた割合です。10回の着信のうち7回対応すれば、応答率は70%になります。逆に放棄呼率は、着信に応じられなかった比率を意味します。お客様や取引先が企業に連絡を入れた時、いつでも電話がつながれば印象はよくなるでしょう。そのため、コールセンターは、企業のイメージを向上するうえで応答率の高さを重視しています。
具体的な応答率の指標は、100%に設定されない傾向があります。企業の着信数は時間によって異なり、電話が殺到する時間帯に合わせて人員を配置すると、コールが少ない時に人手が余るためです。多くのコールセンターは人員配置の都合から若干の取りこぼしは不可避と考え、その対処策として自動案内に切り替わるシステムを取り入れています。
※関連記事「サービスレベルの低下を意味する放棄呼と対策」はこちら
SL
SL(Service Level:サービスレベル)は、一定時間内に着信対応できた比率です。応答率はトータルの着信数から算出されますが、SLは時間設定が加わります。午前は着信10件のうち7件に応じ、午後は20件のうち16件を処理すれば、それぞれの時間帯のサービスレベルは70%と80%です。コールセンターの着信数は時間によって変動しますが、業務開始直後・お昼前後・業務終了間際に指標を設定すると、各時間のサービスレベルを測定できます。
ASA
ASA(Average Speed of Answer:平均応答速度)は、着信があってから電話に出るまでに要した時間の指標です。電話の着信から応答までの時間が短いほど、発信者を長く待たせなかったことになります。すぐに電話がつながると好印象につながるため、ビジネスの場では「3コール以内に出る」や「10秒以上は待たせない」がマナーにです。
コールセンターにとっても応答時間の早さは重要であり、「何秒で応答できたか」について指標を設定する傾向があります。
※関連記事「コールセンターにおける品質向上のコツとは?」はこちら
生産性・収益性に関する指標
コールセンターの生産性・収益性を上げるうえで重要になっている指標は、稼働率(占有率)やAHT(平均処理時間)です。
稼働率(占有率)
稼働率(占有率)は、オペレーターが電話対応や業務全般に費やしている時間です。電話対応以外の業務を含めるかどうかは、コールセンターによって異なります。業務全般が含まれる場合、「通話時間+保留時間+後処理時間+待機時間+離席時間」でトータルの労働時間がチェック可能です。
一方、電話対応が評価対象であれば待機時間や離席時間が除かれ、どれくらい通話や後処理に時間をかけているかを確認できます。その合計を勤務時間から差し引けば、着信がなく待機する時間や、他の業務に要している時間も見えてくるでしょう。単純に稼働率の指標を高く設定すると電話対応に追われ余裕がなくなるため、その他の時間とバランスを取ることが大切になります。
※関連記事「コールセンターの「稼働率」「応答率」とは?」はこちら
保留時間(保留率)
保留時間(保留率)、電話を受信した後に保留した時間の割合です。多くの発信者は、企業へ電話した時に保留時間が長ければ、「待たされている」と感じます。また、電話対応の効率は下がるでしょう。電話対応の印象や生産性を高めるうえで、保留時間の短縮は重要と考えられます。コールセンターが保留時間の指標を設定した場合、オペレーターが電話を長く保有していないか調べるのに役立ちます。
離席時間(離席率)
離席時間(離席率)は、勤務中のオペレーターが電話対応業務に着手していない時間です。一般的には、業務関係の打ち合わせや新人教育のため、着信対応から離れている時間が相当します。また、コールセンターによっては、休憩時間や有給休暇が含まれるケースもあります。いずれも、電話対応を円滑に進めるうえで不可欠でしょう。とはいえ、これらに長い時間をかけると業務効率は下がるため、目安となる指標の設定が必要になります。
AHT
AHT(Average Handling Time:平均処理時間)は、1回の着信対応にかかった時間の平均値です。具体的には、1つ目の着信で応答を開始してから次の着信に応じるまでの時間が該当します。ここには、1コールあたりの通話時間や保留時間がすべて含まれます。基本的な計算式は、「AHT(分・秒)=通話時間+保留時間+後処理時間÷通話件数」です。着信ごとの処理時間が短ければ業務効率が上がり、顧客満足度の向上や経費節減につながるため、多くのコールセンターで重視されています。
※関連記事「コールセンターのAHT(平均処理時間)とは」はこちら
ATT
ATT(Average Talk Time:平均通話時間)は、1回の着信対応に費やされた通話時間の平均値です。この数値は、「通話にかかった時間の合計÷通話件数」で求められます。1日の通話にトータル300分かかり、通話件数が60件であった場合、平均の通話時間は300÷60=5分です。コールセンターは電話対応が中心業務であり、一般的に通話時間は業務全体のなかで多くの割合を占めます。ただし、平均時間が長いと着信対応できる件数は減少するため、業績指標として目標時間の設定は重要になります。
ACW
ACW(After Call Work:平均後処理時間)は、通話を終えてから後処理に要した時間です。「後処理時間の合計÷通話件数」で、平均時間が算出できます。コールセンターで着信対応した際、通話終了後は電話の用件に関するデータ入力や報告書の作成が欠かせません。ただし、各々の処理作業が長引くと次の着信対応は遅れやすくなり、場合によっては取りこぼす可能性があります。速やかに着信対応するには後処理を効率よく進める必要があり、コールセンターでは後処理時間の指標が設定されます。
CPC
CPC(Cost Per Call:コスト・パー・コール)は、1件の電話対応ごとにかかるコストです。「電話対応の総費用÷通話件数」で、1件あたりの費用が算出されます。電話対応の総費用には、通信費をはじめオペレーターの人件費やオフィスの設備費まで含まれるのが通例です。また、トータルの費用が同じなら、通話件数が多いほど1件あたりのコストは抑えられることになります。そのため、CPCは、1件の電話対応に過大なコストがかかっていないかチェックするうえで重要な指標と理解されています。
一次解決率
一次解決率は、最初の着信対応で顧客からの質問やクレームを解決できた比率です。1回の電話で質問やクレームが解決すれば、顧客満足度は向上すると期待できます。また、同じ用件の電話を何度も受けたり折り返し連絡したりする手間が省かれれば、オペレーターの業務負担は軽減するでしょう。これらの理由から、コールセンターは、一次解決率の高さを業務上の重要な指標と認識しています。
顧客満足度に関する指標
コールセンターが顧客満足度を向上するために設定する代表的な指標は、CS(顧客満足)やNPS(正味推奨者比率)です。
CS
CS(Customer Satisfaction:顧客満足)は、お客様や取引先がコールセンターの電話対応にどれほど満足できたかを示す指標です。この指標は、お客様や取引先に喜ばれる電話対応を実現する際、重要な評価基準になります。ただし通常、顧客が電話対応に満足した度合いは、応答率や通話時間と異なり直接に数値として現れません。そのため、コールセンターに関する顧客満足は、アンケート調査の結果を数値化するケースが多く見られます。
※関連記事「顧客満足(CS)の意味や向上を目指す取り組み」はこちら
NPS
NPS(Net Promoter Score:正味推奨者比率)は、顧客が商品・サービスを周りに推奨したいと考えている割合です。一般的には、特定の商品・サービスを推奨したいと考えているか、アンケート調査が実施されます。その回答結果から、顧客は「推奨者」「中立者」「批判者」に分けられます。
計算式は、「(推奨者数-批判者数)÷回答者数」です。回答者が100人の場合、推奨者60人・批判者20人であれば、正味推奨者比率は「(60-20)÷100=40%」になります。NPSは商品・サービスへの信頼感や愛着度を示す数値と見られるため、コールセンターでは顧客満足度を評価する指標として重視されています。
従業員マネジメントに関する指標
コールセンターが従業員をマネジメントするなかで大切になる指標は、欠勤率や離職率です。
欠勤率
欠勤率は、従業員が各自のシフトを欠勤した割合です。厳密には遅刻・早退の時間も含まれ、「欠勤・遅刻・早退の合計時間÷本来の勤務時間」で計算されます。従業員が仕事を休む理由は、風邪による体調不良やストレスに起因する精神的な不調など多種多様です。いずれの理由でも、欠勤が多いと他の従業員の負担が増えるだけでなく、体調によっては勤務を継続できなくなる可能性があります。
企業が仕事全体を円滑に進めるうえで、従業員が本来のシフト通りに勤務することは大切です。コールセンターでも、人手不足による業務負担の増大や度重なる欠勤が離職につながる事態を防ぐため欠勤率の把握は重要と考えられています。
離職率(定着率)
離職率は、一定期間に従業員が離職した割合です。通常、「特定期間の離職者数÷在籍人数」の式で算出されます。コールセンターはクレーム対応によるストレスなど業務負担が大きく、離職率は高いといわれています。とくに新人オペレーターは、早期に離職するケースが少なくありません。
必要な人手を確保できなければ、電話対応をはじめ各種の業務に支障が出るリスクは増すでしょう。そのため、多くのコールセンターは、教育体制の充実化やアルバイトの正社員登用によりオペレーターの定着率向上を目指しています。それぞれの項目でオペレーターが指標に近い成果を上げていけば、コールセンターにおける最終目標の達成度は上昇すると期待できます。
※関連記事「オペレーターの定着率・離職率について」はこちら
施策を成功させるためにはPDCAが重要
コールセンターが業績評価の指標を設定して業務改善を成功させるには、PDCAを実行することが重要です。
PDCAの概要
PDCAは、様々な業務を円滑に進める手順のひとつです。それぞれの文字は、以下の意味を有しています。
| P(Plan) | 目標設定 |
|---|---|
| D(Do) | 目標に沿った施策の実施 |
| C(Check) | 施策の効果を検証 |
| A(Action) | 問題点の改善・解決 |
この手順では最初に目標を設定し、目標達成に向けた施策を実施します。さらに、どれほど施策が効果を上げたか検証し、そこで判明した課題の改善・解決を進める流れです。以上の手順を繰り返すことで、各種業務は徐々に生産性が上がり、目標達成に近づくと理解されています。
PDCAの大切さ
コールセンターが業務改善を進める際にも、PDCAは大切と考えられます。それぞれの業務で目標が設定された場合、オペレーターは目標達成を目指して業務に励みやすくなるでしょう。応答率や通話時間の明確な指標が示されれば、目的意識をもって各種業務に取り組めると期待できます。
ただし、すぐに十分な成果が上がるとは限りません。多くの場合、最初の目標設定に問題がないかを検証する作業が必要になります。コールセンターでも、実現の難しい指標が設定され、見直しを迫られるケースが見られます。コールセンターが適切な指標の設定により業務改善を成功するためにも、目標設定から課題の解決までを繰り返すPDCAは重要になるでしょう。
※関連記事「PDCAサイクルを回して仕事の効率を上げるには」はこちら
電話代行サービスについて
企業で電話対応の体制を整えることが難しい場合、電話代行はコールセンターとして活用できるサービスです。電話代行は、職場に着信があれば、オペレーターが一通りの電話に対応するシステムです。人手不足で社内の電話対応が間に合っていない時も、着信時の応答率は高まると見込めます。
また、オペレーターは常に迅速・的確な着信対応を心がけているため、お客様からの質問やクレームはスムーズに処理できるでしょう。通話に長い時間がかかる心配はなく、一次解決率は向上すると期待できます。これから社内に電話の受付窓口を設置するなら、応答品質や生産性が高いコールセンターとして機能する電話代行の活用はおすすめです。
この記事を読まれている方へのオススメ
>>コールセンターに営業代行を依頼しよう!費用の相場や選び方を紹介
>>コールセンター業務の倫理規定やガイドライン
>>コールセンターのSV(スーパーバイザー)の役割
最新記事 by 電話代行サービス株式会社広報部 (全て見る)
- 「横浜045番号」をレンタル!全国電話番号貸出サービス - 2025年7月2日
- 「電話対応に強い」カスタマーサポート代行8社比較 - 2025年6月30日
- 社労士事務所の電話対応は「電話代行サービス」が解決! - 2025年6月27日


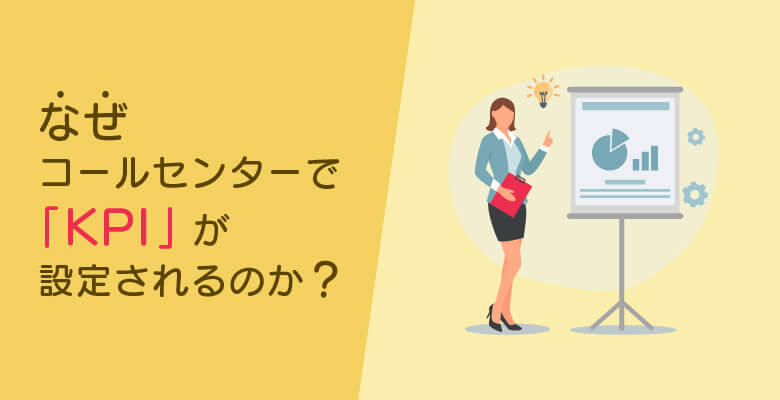

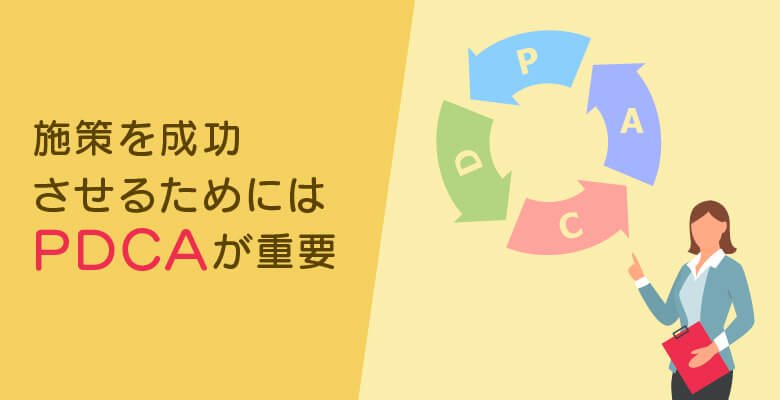
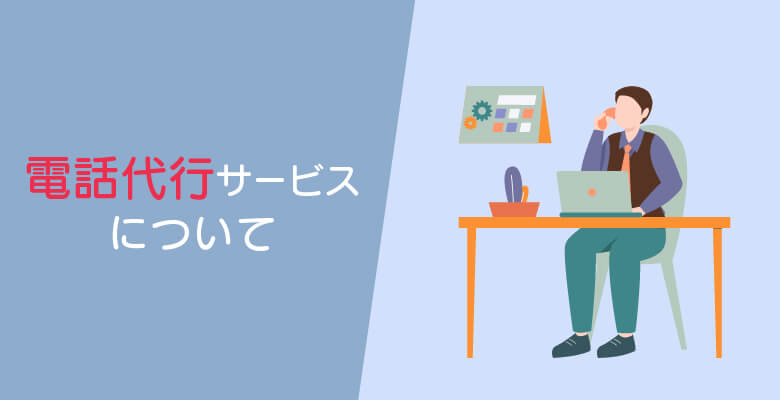
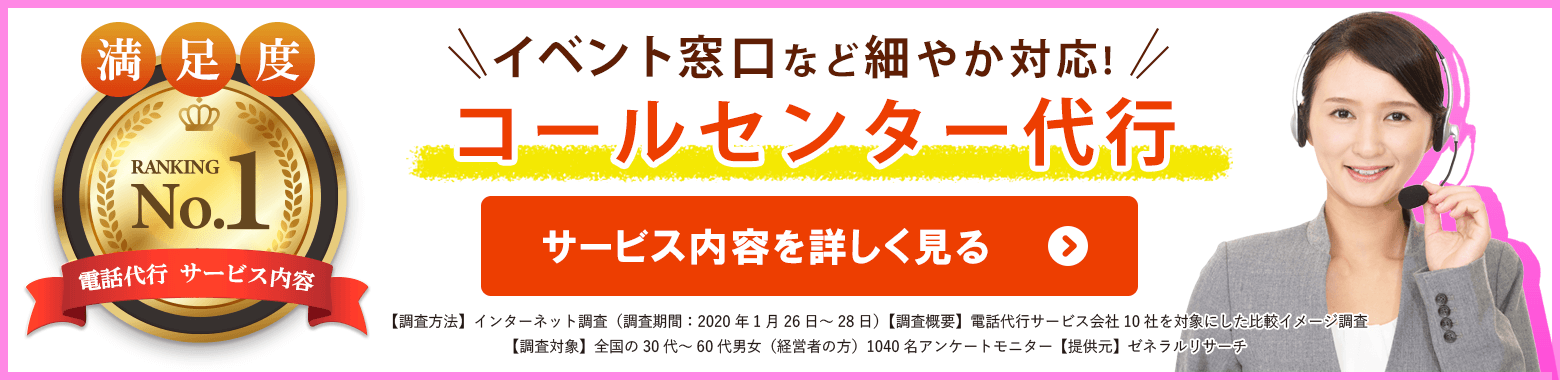

 コールセンターで共有する顧客との“共通語”
コールセンターで共有する顧客との“共通語” コールセンター志望者必見!発声法や笑顔の作り方
コールセンター志望者必見!発声法や笑顔の作り方 今、注目のコーチングとは?オペレーターの育成法
今、注目のコーチングとは?オペレーターの育成法 コールセンターの仕事で伸ばせるスキル7つ
コールセンターの仕事で伸ばせるスキル7つ コールセンター代行をパワハラ相談の窓口に
コールセンター代行をパワハラ相談の窓口に 緊急時に活躍できるオペレーターになるには
緊急時に活躍できるオペレーターになるには