心に残る送別会のスピーチ【送る側・送られる側の例文付き】
更新日:2025.12.22 / 公開日:2018.03.01スタッフブログ , 秘書代行 , 電話代行企業や職場の送別会では、送る側と送られる側ともに、よく挨拶・スピーチを求められます。その際、心に残るような言葉を贈りたいが、何を話せばよいか悩むとの声は多く聞かれます。この機会に、いろいろな例文を確認しておけば、送別会で挨拶しやすくなるでしょう。そこで今回は、送別会の基本マナーをふまえ、さまざまなケースごとに送る側や送られる側の挨拶の例文をご紹介します。
【関連記事はこちら】
>>育休・産休に入る人へのメッセージ
目次
送別会の基本マナー
送別会は、いまの職場から離れる方を気持ちよく送り出すことが、大切な基本マナーです。送る側が挨拶する時は、適切な言葉を選び、感謝や労いの気持ちを伝える姿勢が求められます。
基本的な流れ
送別会の基本的な流れは、次の通りです。
1.開会の言葉
2.代表の挨拶
3.乾杯の挨拶
4.食事・歓談
5.送る側の挨拶
6.プレゼント贈呈
7.送られる側の挨拶
8.締めの挨拶
9.閉会の言葉
最初は、送別会の幹事が開会の言葉を述べ、続いて最も立場が上となる参加者に代表の挨拶をお願いします。その後は、乾杯を済ませ食事や会話を楽しみ、送る側が挨拶してプレゼントを贈呈する流れです。送別会の主賓である送られる側には、プレゼントを贈呈したタイミングで挨拶してもらいます。
一通りイベントを終えてから挨拶をしたほうが、送られる側の言葉が参加者の記憶に残りやすくなるためです。送る側と送られる側が挨拶した後は締めの挨拶が続き、幹事による閉会の言葉で送別会は終了します。
以上は基本的な流れであり厳密なルールはありませんが、送られる側が主賓であり、送別会の最終盤で挨拶を頼む配慮は大切になります。
挨拶は誰がする?
乾杯や締めの挨拶は、参加者のなかでも立場が高めの人に頼むケースが一般的です。送別会の場合、最初の乾杯は立場が3番目の参加者に挨拶してもらうのが慣例となっています。企業や職場によっては、送られる側の直属の上司にお願いする場面も見られます。
一方、送別会の締めの挨拶は、通例として2番目に立場が高い参加者の担当です。最も立場が上の参加者には代表挨拶を頼む場合が多く、乾杯と締めの挨拶は、一般的に2番目と3番目の参加者に分担してもらいます。なお、その場で頼むと失礼に思われる可能性があるため、事前にお願いしておく配慮は不可欠といえます。
送る側の挨拶例文
送別会での送る側の挨拶は、これまでの感謝や今後の活躍に期待する気持ちを伝えることが大切です。
上司へ
職場を離れる上司への挨拶は、言葉遣いに注意しながら感謝の言葉を述べます。
例文1:転勤、異動
〇〇部長、長いこと大変お世話になりました。
入社以来、失敗の連続でしたが、いつも温かい言葉に励まされてきました。ようやく仕事で成果を出せた時、「ずっと信じていた」と評価してくださったことは、いまでも忘れられません。
職場が離れるのは少し寂しいですが、部長の信頼に応えるため、これからも一生懸命に頑張ります。
新天地でも、お身体に気をつけて、さらに活躍なさってください。また、機会があれば、ご一緒に仕事できることを楽しみにしております。改めて、心温まるご指導、本当にありがとうございました。
例文2:転職
〇〇課長、このたびはご転職、誠におめでとうございます。
課長には、何度も励ましの言葉を頂戴し、感謝しかありません。とくに、新しいプロジェクトを任され不安だった時、「責任は取るから、安心して」の一言に支えられたことは鮮明に覚えています。
別の業種へ転職されるのは寂しく感じますが、これまで学んできたことを活かしながら頑張っていきます。
新天地でも、健康に配慮され、より一層ご活躍ください。〇〇課長のもとで働けたことは、とても誇らしく思います。入社から〇年間、ずっとご指導くださり、本当にありがとうございました。
上司への挨拶は、上手に言葉を選べば、どれだけ感謝の気持ちが大きいか明確に伝えられると期待できます。
同僚へ
同僚に向けた挨拶は、親しみやすい表現を意識するのが大切なポイントです。
例文1:転勤、異動
〇〇さん、〇年間お世話になりました。
入社時から〇〇さんと一緒に働けて、本当によかったと思っています。新規プロジェクトの企画について夜遅くまで議論したり、二人で営業先を走り回ったりしたことは、大事な思い出です。
大切な仕事仲間が転勤するのは寂しいですが、〇〇さんなら、新しい職場でも活躍されると信じています。これからも、お互い頑張りましょう。〇年間、本当にありがとうございました。
例文2:転職
〇〇さん、このたびはご転職、おめでとうございます。
これまで〇年間、〇〇さんと同じ職場で働けて、とても楽しかったです。いつも、仕事や私生活の悩みを親身に聞いてくれたので、何度も助けられました。共通の趣味で盛り上がれたことも、よい思い出となっています。
〇〇さんとは多くの思い出があるので転職は寂しいですが、これからも応援しています。仕事が変わっても、これまで通り連絡してもらえると嬉しいです。本当に、ありがとうございました。
親しい同僚に挨拶する時は、お互いにとって印象深いエピソードを話すと、心に残りやすくなるでしょう。
部下へ
部下に挨拶する時は、感謝や励ましの言葉を贈ることが望まれます。
例文1:転勤、異動
〇〇さん、これまでお疲れ様でした。
いつも、出勤中に顔を合わせると、明るく挨拶してくれてありがとう。大量の仕事に追われ頭を抱えていると、すぐに「手伝いますよ」と声をかけてくれたので、頼もしく感じていました。
新しい職場への異動は不安もあると思いますが、〇〇さんの周りを気遣う姿勢があれば大丈夫でしょう。さらなる活躍を、楽しみにしています。〇年間、本当にありがとうございました。
例文2:転職
〇〇さん、このたびはご転職、おめでとうございます。
入社当時から、どんな仕事を頼んでも真剣に取り組んでくれたので、たくさん見習うところがありました。また、いつも最後まで粘り強く作業する姿勢は、よく記憶しています。
〇〇さんの真面目な性格と忍耐強さは、新しい仕事でも、大きな武器になると思います。今後も、自分の強みを活かしてご活躍ください。これまで〇年間、本当にありがとうございました。
大切な部下には、これからの活躍に期待する気持ちを伝えれば、心強い励みになると考えられます。
寿退社する方へ
寿退社する方への挨拶は、何より祝福の言葉を贈ることが大事です。
例文
〇〇さん、このたびはご結婚、誠におめでとうございます。
また、〇年間、大変お疲れ様でした。
いつも、仕事でミスするたびに温かい言葉で励ましてくださり、本当にありがとうございました。周りに細やかな気配りができる〇〇さんと一緒に働けて、心からよかったと思っております。
これからは、新しい人生を歩まれることとなりますが、ぜひ素敵なご家庭を築いてください。〇〇さんのご多幸を、心よりお祈りしております。改めて〇年間、本当にありがとうございました。
寿退社する方には、感謝の言葉を添えてお祝いの気持ちを伝えると、喜んでもらえるでしょう。
定年退職する方へ
定年退職する方へは、これまでの感謝と労いの言葉を伝えることが重要です。
例文
〇〇部長、長い間、大変お世話になりました。
まだ仕事に不慣れな頃から、ずっと温かく見守ってくださったこと、心から感謝しております。仕事ができるだけでなく部下にも優しい部長には、何度となく助けていただきました。
もうご指導いただけないのは寂しい限りですが、今後は、部長から学んだことを糧に頑張ります。
これからの人生は、お身体を大切に、ご家族と過ごす時間をゆっくりとお楽しみください。今後のご健勝とご多幸を、心より祈念いたします。〇年間の長きにわたり、本当にありがとうございました。
定年退職する方への挨拶は、感謝・労いの言葉とともに新たな人生へのエールも送ると、好印象につながります。
送られる側の挨拶・お礼
送別会で送られる側がスピーチする際は、参加者へのお礼や感謝を伝えるのが基本です。スピーチの時間は限られるため、話す内容は、短めにまとめると無難でしょう。
例文1
本日は、お忙しいなか、このような素晴らしい会を催してくださり誠にありがとうございます。
また、皆様と一緒に働かせていただき、感謝しております。
この〇年間は、優しい上司と頼もしい同僚や部下に恵まれ、実りの多い日々を過ごすことができました。どれだけ会社に貢献できたかは分かりませんが、ここまで成長できたのは、皆様のおかげです。
これから職場は変わりますが、機会があれば、また一緒に仕事できることを楽しみにしております。最後に、会社のさらなる発展と皆様のご活躍をお祈り申し上げます。本日は、本当にありがとうございました。
例文2
皆様、本日は、お忙しいなか私のために素晴らしい会を開いてくださりありがとうございます。
また、先程は温かい激励の言葉をいただき、感謝いたします。
入社してから〇年間、いつも上司や同僚が温かく見守ってくださったので、今日まで楽しく仕事を続けられました。新しい世界に進もうと決意できたのも、皆様に力強く背中を押していただけたからです。
今後は、この会社で教わったことを支えとして、少しでも成長できるように努力していきます。これからも、応援していただけたら嬉しく思います。本日は、本当にありがとうございました。
送られる側の挨拶では、送別会へのお礼とともに仕事面の感謝も述べると、参加者の印象はよくなるでしょう。
送別会の締めの挨拶例文
送別会の締めの挨拶は、職場を去る人が前向きになれる気持ちのよい言葉を贈ることが重要です。
例文1
〇〇部長、これまで大変お疲れ様でした。長年にわたりご尽力くださったこと、従業員一同、深く感謝しております。これからも、時間があれば、いつでも顔をお見せください。今後の益々のご健勝とご活躍を、心より祈念いたします。
例文2
〇〇さん、〇年間、大変お世話になりました。新しい職場でも、より一層ご活躍されることを願っております。今後も、健康に気をつけて頑張ってください。さらなるご健勝とご活躍を、お祈り申し上げます。
例文3
〇〇さん、長いこと大変お疲れ様でした。従業員一同、〇〇さんの新しい人生の門出をお祝いできたこと、とても嬉しく感じております。これからの益々のご健勝とご多幸を、心よりお祈りいたします。
締めの挨拶も、職場から去る方を気持ちよく送り出すためのものであり、感謝や労いの気持ちが伝われば十分です。
以上はあくまで例文に過ぎませんが、送別会の挨拶で何を話すか迷った時などは参考にしてください。
今後の人手不足の課題解消には電話代行を
企業・職場が従業員の転勤や退職で人手不足になった際、電話代行は、課題を解消するのに有効です。
【関連記事はこちら】
>>電話代行とは?
以下では、企業や職場の人手不足の解消策としての電話代行のメリットをご紹介します。
退職による影響
企業の従業員が退職すると、社内は人手不足に悩まされる可能性があります。昨今、国内の労働力は減少する傾向にあり、さまざまな業種で人員確保は難しくなりました。社内の従業員が職場を去った時も、新しい人員の補充は容易でなく、人手不足の問題が起きやすくなっています。その結果、企業・職場によっては、従業員が足りず業務に差し支えるといった影響が出ています。
電話代行のメリット
電話代行は、企業や職場の人手不足を解消するのに役立つサービスです。企業が電話代行を導入した場合、職場に電話があった時、着信時の一次対応は代行会社のオペレーターに任せられます。社内の従業員は電話に出る手間が省けるため、それぞれの担当業務に専念しやすくなります。
社内の人手が少なくても電話対応に追われなくなる点は、電話代行がもたらす大きなメリットです。従業員が各々のコア業務に集中しやすくなれば、社内の業務効率向上につながるでしょう。従業員の退職で人手不足に直面した時は、課題解消策として、ぜひ電話代行の活用をご検討ください。
【関連記事はこちら】
>>人手不足解消の近道に電話代行が有効な理由
最新記事 by 電話代行サービス株式会社広報部 (全て見る)
- 【シーン別例文付き】電話対応の敬語使い方完全ガイド - 2026年2月6日
- 個人タクシーに電話代行は必要?予約取りこぼし対策術 - 2026年2月4日
- 不明着信は出るべき?機会損失を防ぐ電話代行の効果 - 2026年1月30日

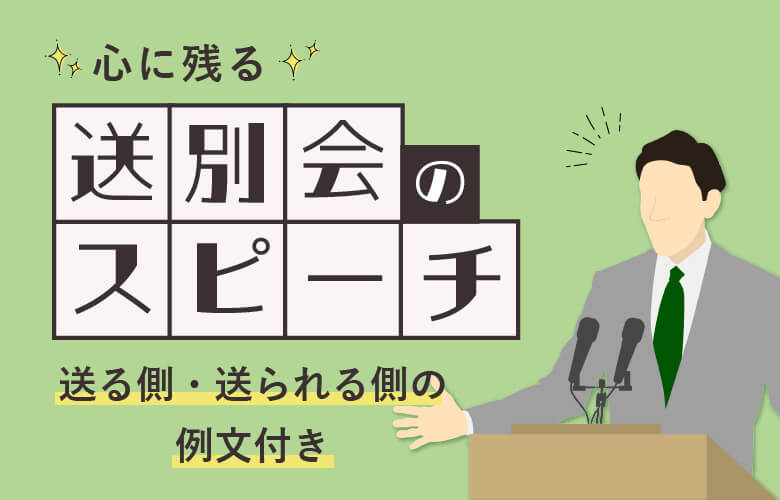


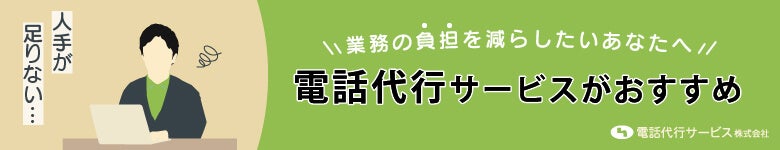
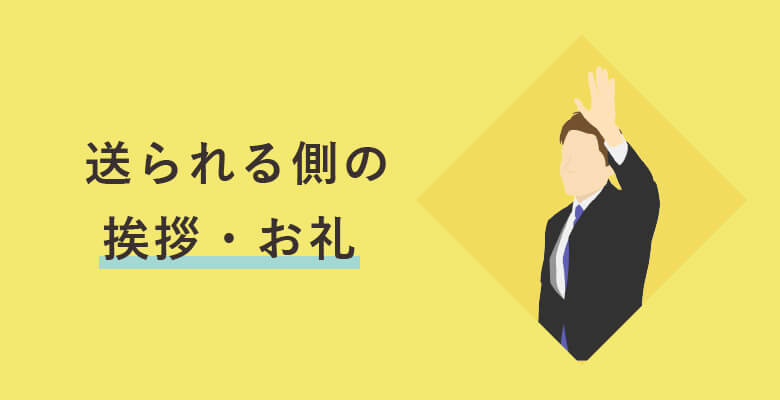
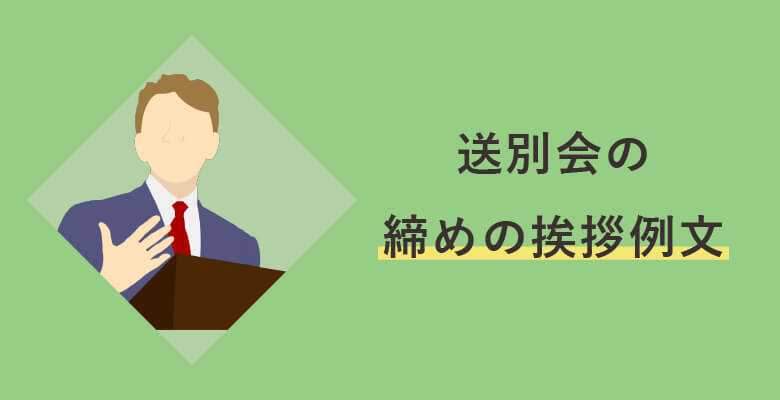
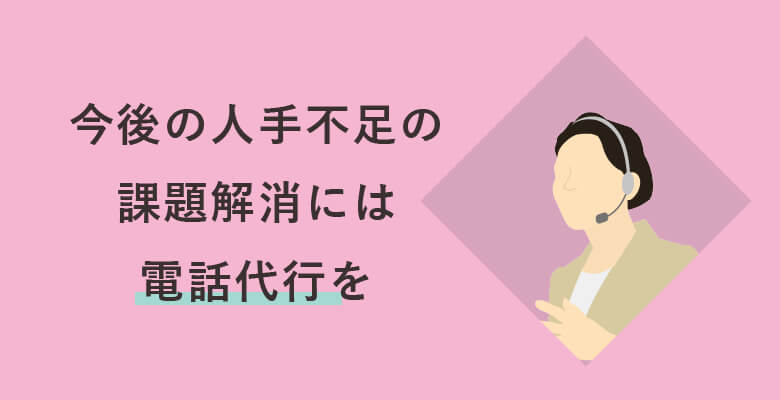
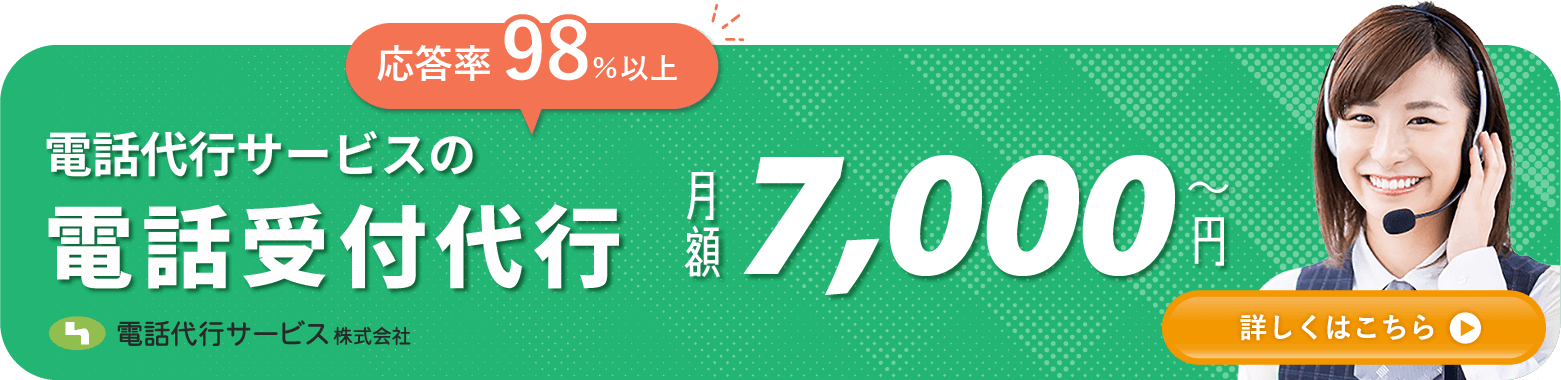

 秘書の必須スキル「営業電話の断り方」「電話アポイントメントの取り方」
秘書の必須スキル「営業電話の断り方」「電話アポイントメントの取り方」 私書箱とは?企業にとってのメリットを解説
私書箱とは?企業にとってのメリットを解説 昼休みの行動はどこまで許される?休憩時間は外出禁止!?
昼休みの行動はどこまで許される?休憩時間は外出禁止!? 電話代行の一次対応、一次受付とは?外注前のチェックポイントを解説
電話代行の一次対応、一次受付とは?外注前のチェックポイントを解説 【スポーツの日】イベント・販促で忙しい担当者向け!解決には電話代行を
【スポーツの日】イベント・販促で忙しい担当者向け!解決には電話代行を 顧客満足度を上げる行動とは?接客で大事な5つの”心がけ”
顧客満足度を上げる行動とは?接客で大事な5つの”心がけ”