Z世代はなぜ電話が怖い?世代別あるあるで読み解く電話マナー
更新日:2025.11.17 / 公開日:2025.09.01業界関連情報 , 秘書代行 , 電話代行「電話が鳴ると胸がざわつく」――そんなZ世代の声が注目を集めています。一方で、昭和や平成世代にとっては「電話は出て当たり前」という意識が根強く残り、世代間でギャップを生んでいるのも事実です。社会人に求められる電話マナーは、時代の変化とともに少しずつ形を変えてきました。今や“苦手を根性で克服する”のではなく、“仕組みで補う”のが令和の働き方です。本記事では世代別の「電話あるある」を振り返りながら、電話応対の背景と解決策を解説します。電話に苦手意識を持つ方も、無理なく働きやすさを保つヒントが見つかるはずです。電話対応にストレスや苦手意識を感じるなら、電話代行サービスをご活用ください。
目次
昭和・平成・令和でこんなに違う?電話マナーの変遷
電話の常識は時代とともに大きく変わってきました。昭和では「必ず出るのが礼儀」とされた電話も、平成では「3コール以内がマナー」、令和では「出られないときは折り返せばOK」と捉え方が柔軟になっています。名乗り方やメモの取り方、さらには他の連絡手段の活用まで、世代ごとに「当たり前」は異なります。下記の比較表では、昭和・平成・令和それぞれでの電話マナーの違いを一覧化しました。
【電話マナーの変遷:昭和・平成・令和 対比表】
※横にスクロールできます。
| 項目 | 昭和 | 平成 | 令和 |
|---|---|---|---|
| 電話は… | 必ずすぐ出るのが礼儀 | 3コール以内に出るのがマナー | 出られないときは折り返しでOK |
| 名乗り方 | 「○○部の△△です」 | 「お世話になっております、△△です」 | 「会社名・氏名・用件」を簡潔に述べる |
| メモの取り方 | 紙とペンで即メモ | メモを取り、上司へは口頭報告 | 録音やチャット共有が一般的 |
| 要件の伝え方 | 雑談から入る | 定型のマナーに添って話す | 用件を先に、手短に話す |
| 電話の心理 | 早く出ないと怒られる・評価が下がる | 慣れて当然・練習あるのみ | 出られなくてもOK・代替手段も活用 |
| ほかの連絡手段 | 電話・FAXがメイン | 電話+メール | メール・チャット・SNSが主流に |
| 上司の対応 | 電話に出ないと叱る | 出て当然と教える | 電話が苦手でも責めない風潮へ |
この表から読み取れるのは、電話マナーが時代とともに大きく変わってきたという点です。昭和は「必ず出る」「紙でメモ」など礼儀を重んじる形式的な文化、平成は「3コール以内」「定型マナー」など効率性と習慣が重視されました。そして令和では「出られなくてもOK」「録音やチャット共有」など、柔軟で仕組みに頼るスタイルが主流になっています。Z世代が「電話が怖い」と感じるのは特別ではなく、価値観や働き方の変化が背景にある自然なことだといえるでしょう。
昭和・平成・令和世代別の「電話あるある」
世代ごとに“電話あるある”を比べてみると、時代背景やコミュニケーション手段の違いがはっきり浮かび上がります。昭和世代は「必ず出る」「紙とペンでメモ」といった緊張感のある対応、平成世代は「3コール以内」「メモ必須」などルール化されたマナーが重視されてきました。一方、令和(Z)世代は「電話は苦手」「テキストで送ってほしい」と感じる傾向が強く、電話そのものにハードルを抱えていることが特徴的です。
※横にスクロールできます。
| シーン・テーマ | 昭和世代あるある | 平成世代あるある | 令和和(Z)世代あるある |
|---|---|---|---|
| 電話が鳴ったとき | 「一番にとらなきゃ!」ダッシュで受話器 | 「3コール内に出ないと怒られる」内心プレッシャー | 「え、誰……?」スマホに出るより勇気がいる |
| 名乗り | 「○○の△△です!」早口でフル名乗り | 「お世話になっております!」何度も練習した | 「会社名?苗字?……あれ。どこまでいえば正解?」 |
| メモ対応 | 「紙とペン」は必須 内容を聞き逃せない緊張感 |
「電話=メモ」がルール | 「録音ないの?チャットでいいじゃん……」 |
| 心の声 | 「電話対応こそ新人の仕事」 | 「何度も出て慣れろ」 | 「電話対応って、スキル?恐怖体験?」 |
| 折り返し | 「こちらから折り返すのが礼儀」 | 「すぐに折り返せないと落ち着かない」 | 「かけ直すの怖い……内容テキストでくれ……」 |
| ほかの連絡手段 | 電話・FAXがメイン | 電話+メール | メール・チャット・SNSが主流に |
この表から読み取れるのは、電話に対する意識が“礼儀→ルール→心理的負担”へと移り変わってきたことです。Z世代が電話を怖いと感じるのは単なる弱さではなく、時代とともに育ったコミュニケーション文化の違いに根ざしています。だからこそ、無理に矯正するのではなく、仕組みとして電話代行などを活用することが自然な解決策になっていくのです。
令和時代の“正解”電話マナー
テレワークや地方移住など働き方が多様化した今、電話マナーも「礼儀」や「ルール」に縛られる時代から、柔軟さと効率性を重視する方向へと進化しています。ここでは、令和時代に求められる“新しい電話マナー”の考え方を整理します。
①出たくない・出られない人への配慮が“新マナー”
令和の働き方では、オンライン会議中や移動中で電話に出られないことは珍しくありません。相手が出られない状況を尊重し「無理に出なくてもいい」「後で折り返せばいい」という配慮が、今のマナーです。メッセージやチャットで補うことも自然な対応とされています。
②「一言で名乗る」「最初に目的を伝える」など効率重視のマナー
昭和・平成時代の「長めの挨拶」よりも、令和は“簡潔で分かりやすい”ことが重視されます。「会社名+氏名+用件」を一言で伝える、要件から話すといった効率的な会話が、相手の時間を大切にする現代的マナーです。
③上司・先輩側が「強要しない」ことも含めて令和のマナー
Z世代を中心に「電話が怖い」と感じる人が多い今、上司や先輩が「出て当たり前」「慣れろ」と強要するのは逆効果です。電話が苦手な部下に代行ツールや役割分担を用意し、無理なくスキルを補える環境を整えること自体が“令和型マナー”だといえるでしょう。
電話代行サービスという選択肢
世代間ギャップによる“電話マナー問題”は、もはや個人の努力だけで解決するのは難しい時代になっています。そんな背景から注目されているのが、電話代行サービスです。業務の一部をプロに任せることで、若手社員を守りつつ企業の信頼性も維持できる、新しい働き方のサポートツールです。
「マナー問題から解放される」若手支援ツールとしての電話代行
電話応対に不安を感じる若手社員にとって、「電話が怖い」という心理的負担は大きなストレス要因です。電話代行を導入すれば、顧客対応をプロに任せられるため、社員は自分の業務に集中可能。新人教育の負担軽減や離職防止にもつながり、企業にとってもプラスの効果が期待できます。
「全部を任せなくてもOK」一時受付など柔軟な運用事例
電話代行は「全業務を外注する」ものではありません。たとえば、求人応募の受付やクレーム一次対応など“特定のジャンルだけ”を任せることもできます。必要な範囲だけ切り出すことでコストを抑えつつ、社員の負担軽減や対応品質の安定化を実現できるのが特徴です。
時代とともに変化してきた電話マナー。昭和世代にとっては「必ず出るのが礼儀」だった電話も、平成世代では“習得すべきスキル”。令和のZ世代にとっては“できれば避けたい業務”へと位置づけが変わってきました。どの世代が正しいということではなく、働き方の多様化とコミュニケーション手段の進化により「電話をどう扱うか」が大きく変わったのです。
こうした時代背景をふまえると、電話対応を“根性論”で押し付けるより、電話代行サービスを導入して仕組みで解決するのが合理的です。社員の負担を減らしつつ企業の信頼性を守る――これが令和時代の新しいスタンダードといえるでしょう。
弊社・電話代行サービス株式会社は、創業以来30年以上にわたり、多様な業種・企業様の電話応対をサポートしてまいりました。単なる電話の取り次ぎだけでなく、採用応募の受付、クレーム一次対応、顧客からの予約・注文対応など、お客様のニーズに合わせた柔軟なサービス設計が可能です。
また、御社名での自然な応対やメール・チャットでの即時報告など、現代の働き方にマッチした仕組みを整えております。若手社員の電話負担を減らし、組織全体の効率化・信頼性向上を図るパートナーとして、ぜひ弊社のサービスをご活用ください。
【関連記事はこちら】
>>Z世代に電話対応は難しい?
最新記事 by 電話代行サービス株式会社広報部 (全て見る)
- 電話代行でCL(顧客ロイヤリティ)改善へ~一次応答体制の作り方~ - 2026年1月23日
- ら抜き言葉・い抜き言葉とは?意味と違いをわかりやすく解説 - 2026年1月21日
- 作業中・夜間の電話取り逃しを防ぐ!カギ交換特化の24時間電話代行とは - 2026年1月14日

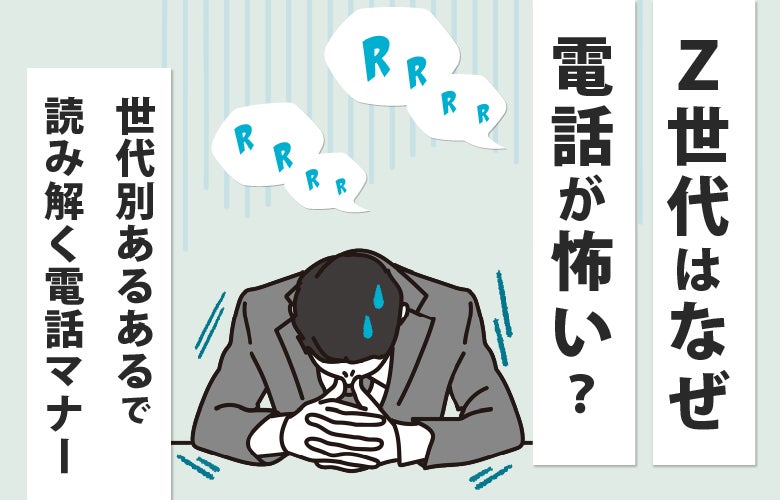
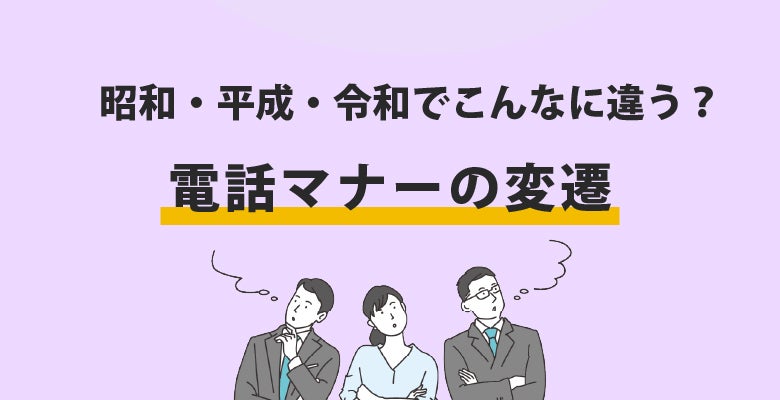
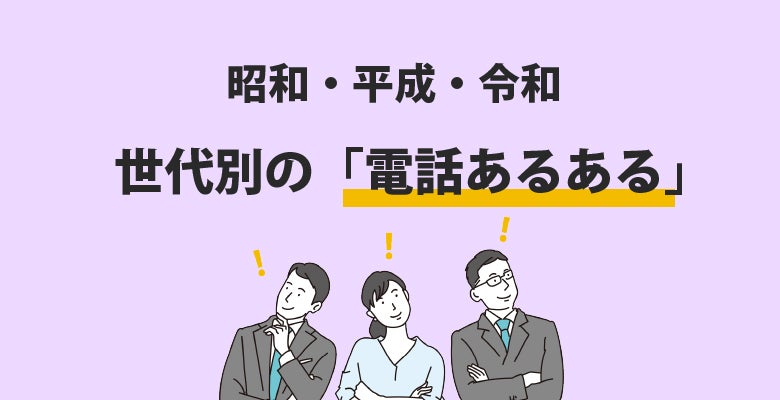

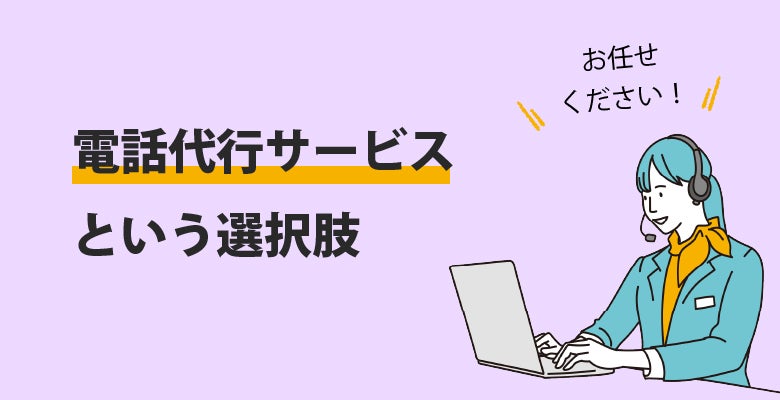
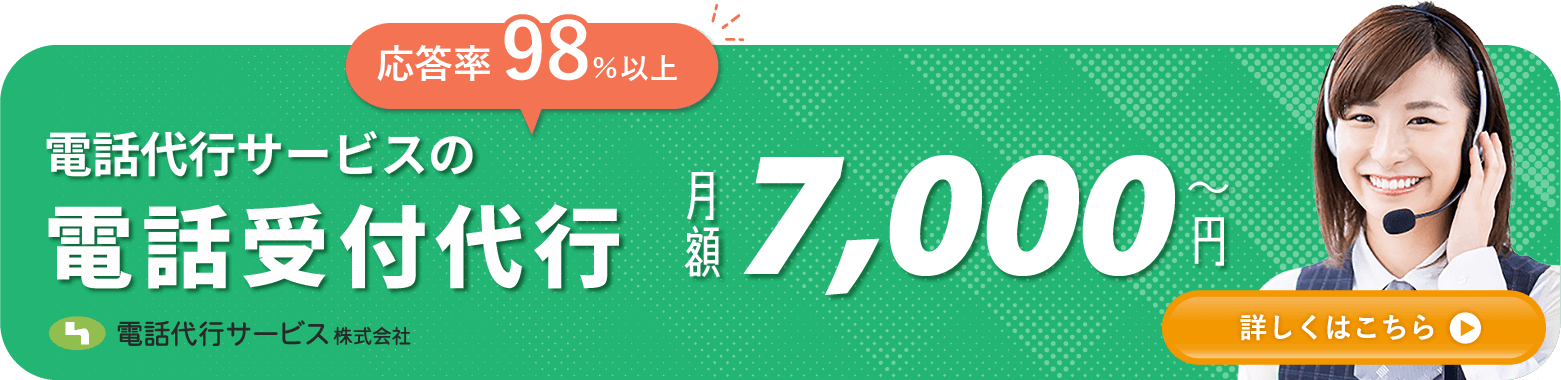

 営業時間外の電話対応はどうする?対処法や気をつけるポイント
営業時間外の電話対応はどうする?対処法や気をつけるポイント 秘書の必須スキル「営業電話の断り方」「電話アポイントメントの取り方」
秘書の必須スキル「営業電話の断り方」「電話アポイントメントの取り方」 個人事業主・フリーランス必見!電話対応は電話代行サービスへ
個人事業主・フリーランス必見!電話対応は電話代行サービスへ 司法書士の繁忙期には電話代行の活用がおすすめ
司法書士の繁忙期には電話代行の活用がおすすめ 格安電話代行に乗り換えたい方へ!電話代行サービスがおススメな理由
格安電話代行に乗り換えたい方へ!電話代行サービスがおススメな理由 プレディクティブコール導入でコールセンター開設をスムーズに
プレディクティブコール導入でコールセンター開設をスムーズに