震災を体験した企業から学ぶ…東日本大震災から14年、電話代行の重要性
更新日:2025.03.28 / 公開日:2025.02.03電話代行本年2025年は、2011年に起きた東日本大震災から14年になります。3月11日が近づくと、震災当時のことを思い出す人は少なくないかもしれません。また、企業にとっては、自社のBCP対策を見直す機会になると考えられます。その際、被災した企業の体験から学ぶことは多いでしょう。そこで今回は、東日本大震災における企業の通信課題をふまえ、震災時の体験談を振り返りながら、BCP対策として電話代行を導入するメリットや重要性をご紹介します。
【関連記事はこちら】
>>BCP対策の連絡手段に電話代行を
目次
東日本大震災における企業の通信課題
東日本大震災で企業が直面した通信関連の課題としては、通信インフラの脆弱性や業務継続への影響が挙げられるでしょう。
通信インフラの脆弱性
2011年3月11日に発生した東日本大震災では、多くの企業が、通信インフラの弱さを認識したといわれています。総務省の報告によれば、この震災で通信インフラが受けた被害は甚大でした。震災発生時、通信ビルの設備・電柱・地下ケーブル・架空ケーブルや携帯電話基地局は、地震や津波により倒壊・断裂や流失といった事態に見舞われたと発表されています。
具体的なデータを示すと、固定電話など固定通信網の通信回線は、主要な通信事業者で約190万回線が被災しました。また、携帯電話やPHSといった移動通信の被害状況を見ると、約2万9千局の基地局が停止しています。東日本大震災で被災地の通信設備は大きなダメージを受け、通信インフラの脆弱性が浮き彫りになったと指摘されています。
総務省 東日本大震災における情報通信の状況 (参照 2025-01)
参議院 震災をふまえた情報通信分野の課題への取組 (参照 2025-01)
業務継続への影響
東日本大震災の発生時には、電話・メールやインターネットがつながりにくくなる状況も問題視されました。総務省の職員による解説では、震災に伴う通信インフラへの主な影響として、通信設備の被害とともに通信回線の輻輳(ふくそう)も取り上げられています。通信回線の輻輳は、電話やインターネットにアクセスが集中し、回線網が混雑・ダウンする状況です。
震災が発生した当時、国内では、家族・知人の安否や被災状況を確認するため電話・メールやネットへのアクセス数が大幅に増えました。通信需要の急増で各回線は輻輳し、いずれの通信回線も接続しにくくなったとの見解が示されています。ビジネスの場でも通信網の確保に支障が生じ、従業員の安否確認や被害状況の把握が困難になり、業務継続に少なからず影響したと見られています。
J-Stage 東日本大震災における通信被害の状況と今後の対応 (参照 2025-01)
震災時の電話対応に関する企業の体験談
震災時の電話対応について企業からは、従業員の安否確認や顧客対応に苦労したなどの話が聞かれました。
従業員の安否確認の難航
企業の体験談では、従業員の安否確認などに苦労した様子が語られています。東京に本社のある医薬品メーカーは、震災翌日に3人が東北地方へ入り、東北在籍の従業員と連絡を取り始めました。ただし、なかなか連絡がつかない場合もあり、安否確認に1週間を要したといわれています。岩手県のセメント会社は、大船渡市の工場が操業停止になるものの、従業員は無事に避難できました。
ただし、本社から持参したパソコンや衛星携帯電話を十分に利用できず、情報伝達に手間取る事態も発生しています。宮城県に拠点を置くガラス基板や薄膜デバイスの製作所は、日頃の防災訓練が活かされ、全従業員の無事を被災から15分ほどで確認できました。それでも、電話や安否確認システムは使えず、安全に帰宅できたか確かめる方法はなかったとのことです。
また、福島県に本店と多くの支店がある銀行からは、「僚店への電話がつながりにくい状況で、連絡を取るまで時間を要した」「本部は電話がかかりにくい状況で被害状況報告は徒歩で対応」などの声が聞かれました。これらの体験談や現場の声から、従業員の安否確認や情報収集は、被災した企業において難航した様子が伝わってきます。
多くの企業は、被災時の体験から、従業員の安否確認に手間取った状況を問題視したと見られます。国内企業を対象とした調査によれば、震災以降に取り組みを強化した事項で「安否確認の仕組み」は63.4%に達し、最多の回答となりました。
MS&ADインターリスク総研株式会社 東日本大震災から2年|震災を乗り越えた企業の軌跡~その時、企業はどうしたか~ (参照 2025-01)
東邦銀行 東日本大震災の記憶~現場からの声~ (参照 2025-01)
顧客対応の混乱
東日本大震災の被災企業は、顧客対応などが混乱する状況にも見舞われました。長野県の特別養護施設は、東日本大震災の翌朝、強い揺れに襲われ利用者の安全確保が急がれる事態となります。また、地域の避難所に指定されていた同施設へは、近隣から多くの住民が避難してきました。被災当時、勤務中の職員は利用者と避難者の対応に追われ、施設内は混乱したといわれています。
限られた職員で利用者と避難者に対応するなか、事務所では、その日の昼頃まで電話が鳴り続けていました。電話の用件は、利用者の家族からの安否確認や避難所に関する問い合わせです。同時に、施設・利用者が無事か心配した他の職員からも、被災状況を確認する電話が寄せられました。施設近隣に居住していた職員は応援に駆けつけますが、十分な人手の確保は難しかったと語られています。
人手が足りない状況は大きく変わらず、利用者・避難者や電話への対応は、しばらく混乱する状態が続いたとのことです。震災発生時、被災地の通信回線はつながりにくい状況にあり、現地の企業・職場が電話対応に苦慮したとの話はあまり聞かれません。
それでも、通信網が回復するにつれて顧客からの問い合わせは増え、着信対応に追われる事態が生じたと考えられます。東日本大震災が起きた後の状況をふまえると、電話対応の混乱を避けるうえで、災害時も着信受付が適切に進められる体制を整えておくことは大切といえるでしょう。
MS&ADインターリスク総研株式会社 東日本大震災から2年|震災を乗り越えた企業の軌跡~その時、企業はどうしたか~(参照 2025-01)
電話代行導入のメリット
電話代行とは、企業にかかってきた電話を、専門のオペレーターが代わりに応対し、業務をサポートするサービスです。
【関連記事はこちら】
>>電話代行とは?
電話代行の導入が企業にもたらす主なメリットは、災害時の業務継続をサポートできるところなどです。
災害時の業務継続支援
災害時に業務継続を支援できる点は、電話代行に期待される大きな利点です。企業は、さまざまな災害が起きた際、取引先や顧客と連絡を取りにくくなる可能性があります。実際、東日本大震災の発生時には、通信回線の混乱もあり原材料の調達や商品の配送が難しくなったとの声は少なからず聞かれました。
一方、企業が電話代行を導入した場合、災害時にも電話窓口を維持できます。電話代行が稼働していれば、通信手段が失われる心配はなく、関係各所と連絡を取りやすくなるでしょう。被災しても取引先や顧客と連絡がつけば、商品の生産や流通が滞るリスクは減り、業務継続につながると考えられます。
社員の安否確認
電話代行の導入は、災害時に従業員の安否確認を遂行するうえでも有用です。企業にとって従業員は貴重な財産であり、災害時には何よりも人命が最優先と認識されています。とはいえ大規模災害が起きると、従業員の安否確認が難しくなるケースは少なくありません。
その際、電話代行は、企業の経営陣と従業員との橋渡し役として機能することが可能です。災害時に社内の通信網が被害を受けても、電話代行を通じて安否確認の作業を進めていけます。すぐに従業員の無事が確認できて安心感が増せば、業務再開に向けた復旧作業にも力を入れやすくなるでしょう。
人的リソースの確保
企業が人的リソースを確保する方法としても、電話代行は役立ちます。災害時には、道路や交通機関がダメージを受け、従業員が出社できず人手不足になるケースが見られます。東日本大震災の後も、人手が足りない状況は、復旧作業を進めるうえで大きな課題となりました。
それに対し、企業が電話代行を導入すると、着信時の初期対応は代行会社のオペレーターに一任できます。社内の従業員が着信を受ける手間は減り、企業は人手を確保しやすくなります。このように、電話代行は、企業が被災した時に幅広くサポートできる便利なサービスです。そのため、万一の事態に備えるなら、職場への導入はおすすめできます。
BCP対策としての電話代行の重要性
電話代行は利便性の高さが特徴的であり、企業のBCP対策として、重要な役割を果たせると考えられます。
事業継続計画(BCP)の一環
企業が事業継続計画を策定する際、電話代行は、BCPの一環で用いるのに適したサービスです。このサービスは電話対応が中心業務であり、企業への電話がつながりやすくなる点に大きな特徴があります。東日本大震災の発生時、多くの企業は社外と電話連絡を取りにくくなりましたが、この問題を回避するのに効果的です。
また、電話代行に着信時の一次対応を任せれば、社内の従業員は電話対応に追われなくて済むでしょう。人手に余裕が生まれた際、企業はコア業務に労力を回しやすくなるため、早期の業務再開につながると考えられます。何より、電話代行の活用で電話の受付窓口を維持できれば、従業員の速やかな安否確認が可能になります。従業員が無事と分かれば、安心して業務再開の作業を進めていけるでしょう。災害時、電話代行は企業の事業継続に貢献できる可能性が高く、BCP対策としての重要性は大きいと考えられます。
なお、電話代行サービス(株)は、地震など有事への備えが充実している会社です。災害の影響で交通機関が混乱した場合、緊急時の出勤プログラムに切り替えて業務を継続できます。また、停電時の備えとして、高機能蓄電システムも導入済みです。BCP対策で電話代行の導入を考えている場合、危機管理体制が整っている弊社サービスの活用をご検討ください。
【関連記事はこちら】
>>災害時に会社機能を守る!電話代行の活用法
最新記事 by 電話代行サービス株式会社広報部 (全て見る)
- 【シーン別例文付き】電話対応の敬語使い方完全ガイド - 2026年2月6日
- 個人タクシーに電話代行は必要?予約取りこぼし対策術 - 2026年2月4日
- 不明着信は出るべき?機会損失を防ぐ電話代行の効果 - 2026年1月30日

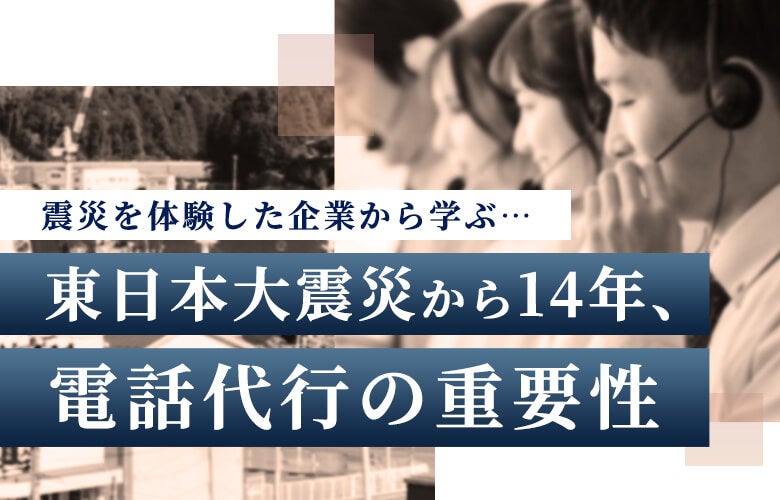
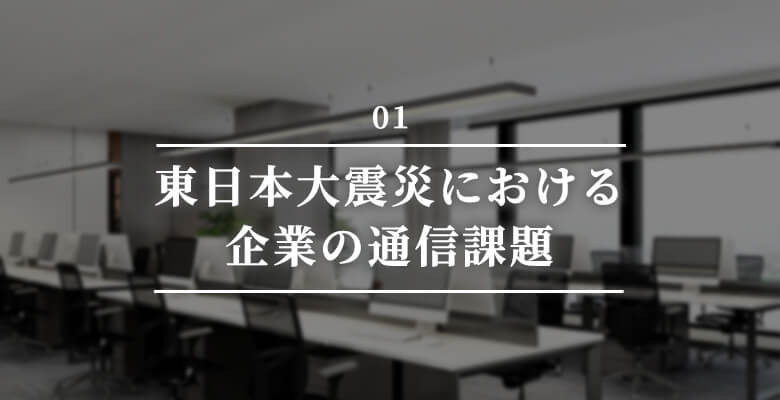


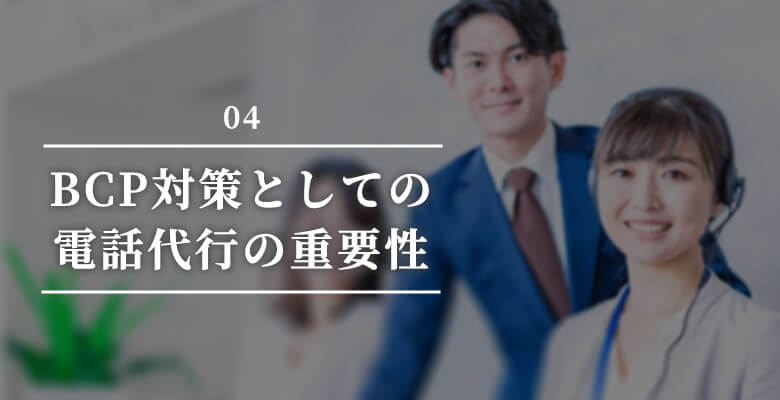
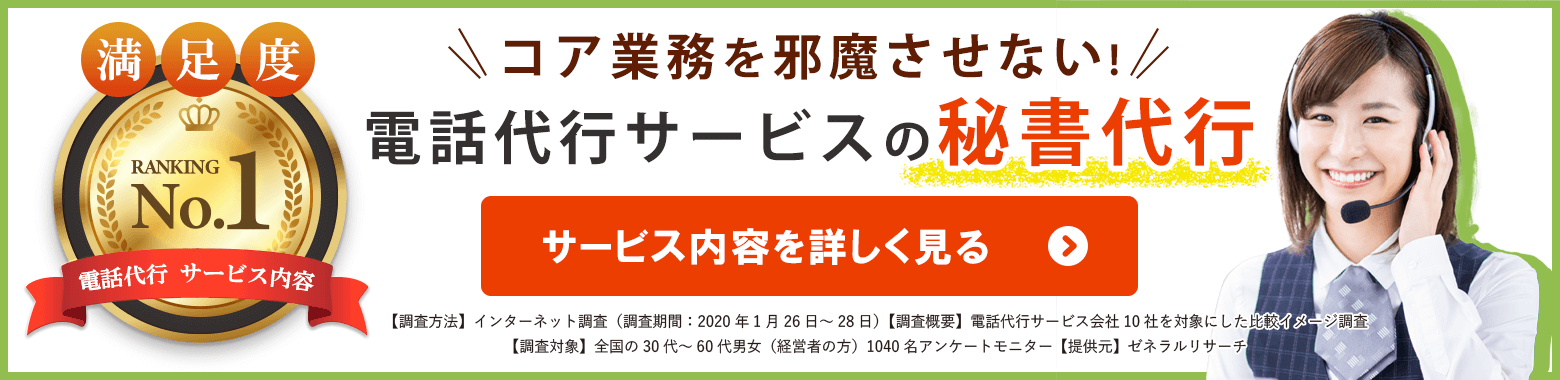

 昼休みの行動はどこまで許される?休憩時間は外出禁止!?
昼休みの行動はどこまで許される?休憩時間は外出禁止!? 士業のテレワーク推進に電話代行を活用
士業のテレワーク推進に電話代行を活用 自然言語処理でコールセンター業務効率は上がる?
自然言語処理でコールセンター業務効率は上がる? 営業電話はいつ連絡しても問題ない?発信を避けたい時間帯や注意点
営業電話はいつ連絡しても問題ない?発信を避けたい時間帯や注意点 6/1は防災点検の日!防災担当者が知っておくべきBCP対策
6/1は防災点検の日!防災担当者が知っておくべきBCP対策 ベンチャー企業が抱える課題を電話代行が解決
ベンチャー企業が抱える課題を電話代行が解決