台風時の出社基準は?~有給問題や計画運休まで徹底解説~
更新日:2025.11.17 / 公開日:2025.06.02スタッフブログ , ビジネス豆知識 , 電話代行夏から秋にかけては、台風が多く発生する季節です。日本に台風が接近すると、企業は従業員の安全と業務継続の両立に悩まされます。実際、会社は台風が接近していても、法律上は従業員に出社を求めることが可能です。しかし、強風や豪雨などの影響で通勤に支障が出ることも多く、トラブルや事故を避けるためには、明確な出社基準を設けておくことが重要になります。そこで今回は、台風接近時の出社命令の可否をはじめ、企業側に求められる出社や早退・休業の判断基準について解説します。さらに計画運休時の注意点、有給休暇との関係までご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
【関連記事はこちら】
>>台風が来るとコールセンターが忙しくなる理由
目次
台風接近時の出社命令はどこまで有効か?
会社は、台風が接近していても、従業員に出社を求めることは可能です。法的には、通勤が困難な気象状況で出社命令を出しても問題ありません。以下では、台風接近時における会社の権利や従業員の義務をご紹介します。
会社側の権利
会社には、原則的に業務命令権があります。これは、従業員に出社・業務を命じる権利です。この権利は、必ずしも雇用条件や就業規則に明記されていません。それでも、会社と従業員の間に雇用関係が成立していれば、効力を発揮します。様々な形で出社困難な状況が起きても、会社側の業務命令権は有効です。台風が接近するケースも例外でなく、会社側は従業員に対して出社命令を出す権利を行使できます。
従業員の義務
会社から出社命令が出された場合、その命令に応じることは従業員の義務です。従業員には労務提供義務があり、原則として出社命令は拒めません。従業員は、会社と雇用契約を結ぶと給料を受け取る立場になり、労務提供義務が発生します。台風で会社が被災した場合、従業員による復旧作業も労務提供義務に含まれます。従業員は契約上の義務を果たさないと懲戒免職になる可能性があるため、台風が接近した時も出社命令に応じるのが基本です。
命の危険がある場合
台風接近時の出社に命の危険があるケースでは、例外的に従業員は出社を拒める場合があります。従業員は、労務提供義務より身の安全を優先することが可能です。命の危険を感じるなか、無理に出社する必要はありません。身の安全を最優先にする考え方は、法的にも認められています。
実際、過去の裁判では、命の危険性を理由に出社命令の違法性が指摘されました。台風の接近時も、命に関わる危険な状況であれば、従業員が出社命令を拒否しても問題ないといわれています。
会社が出社判断を行う際の基準とは?
台風が接近した時、従業員が出社するかどうかの判断は、会社に委ねられています。会社は従業員に対する安全配慮義務があり、十分な配慮が欠かせません。以下では、台風接近時に出社判断の基準として確認したい情報などをご紹介します。
台風接近時の判断基準
台風の接近時、会社が従業員に出社を求めるか決める判断基準は、一般的に「気象情報」と「交通機関の運行状況」の2つです。通常、台風関係の気象情報は、台風の発生から数日にわたり暴風雨の強さや予想の進路がテレビやネット上で伝えられます。また最近、鉄道を中心とする交通機関は、台風接近の前日に運行計画を発表するケースが増えてきました。
都市部の会社は電車やバスで通勤する従業員が多く見られるため、これらの情報は出社判断する際に役立つでしょう。台風が直撃すると予想され交通機関が全面的に止まる見通しであれば、従業員に出社を求めることは難しいと判断できます。これらに加えて、従業員が徒歩・自転車や自動車で通勤している場合に確認しておきたい情報が、警報級の可能性です。
この情報は5時・11時・17時に気象庁から発表され、可能性が高ければ徒歩や自動車での出社は難しいといわれています。台風接近時に会社が出社命令を出すか検討する際、従業員を無理に出社させないためには、気象情報や交通機関の運行状況の確認が重要と考えられます。
会社が休みになる基準
台風の接近で会社が休みになる基準は、各会社の就業規則や独自ルールで定めるケースが一般的です。就業規則や独自ルールでは、いずれの状況で会社を休みにするか事前に決めておく必要があります。台風の危険レベルが高い場合、業務に支障が出なければ出社を求めず休業にするのが適切でしょう。
ただし、納期の迫った業務がある場合、休業するか迷うかもしれません。その場合、取引先に納期延長を打診したうえで、延長できない時は出社を求めるといった手順をルール化しておく必要があると考えられます。また、出社後に台風の勢いが強まると、従業員は帰宅困難になる可能性があります。
台風対策では、従業員が帰宅困難にならないタイミングで早退や半日休業を決める基準の設定も大切です。様々なケースに備えて会社を休業する時の基準をルール化しておけば、台風が近づいても従業員は落ち着いて行動できるでしょう。
交通機関の計画運休基準について
鉄道や飛行機などの交通機関は、台風の接近時に計画運休する基準を定めています。まず、鉄道は、風が強い場合に速度規制する決まりです。JR東日本は、電車の脱線や転覆を避けるため、風速20~25メートルで減速、25メートルを上回る時は運転を中止すると定めています。
飛行機も、強風の時には安全運航が難しくなる交通機関です。規制を受ける風力は状況によって異なりますが、追い風が約8メートルに達すれば、離着陸に制限が発生するといわれています。台風レベルの強風は風速20メートルほどであるため、台風が接近した時は多くの交通機関で通常運行が難しくなると考えられます。
台風の休みは有給休暇扱い?
台風の接近により会社が休業になった場合や出勤が困難になった場合、その休みを「有給休暇扱い」にしてよいのか、疑問に思う方も多いでしょう。結論からいえば、会社の都合や自然災害による休業を理由に、従業員に有給休暇を一方的に使わせることは、基本的に認められていません。
有給休暇は、労働者が自由に取得できる権利であり、会社側が従業員の意思に反して使用させることは原則として違法です。たとえば、台風の影響で交通機関がストップし出勤が難しい場合、それが従業員の責任によらないものであれば、有給休暇の強制使用は不適切といえます。ただし、会社があらかじめ「台風などで業務に支障が出た場合は休業とする」などの就業規則や労使協定を定めていることもあるでしょう。
その内容に従って休業扱いにする場合は、有給休暇を使わずに済むこともあります。一方、従業員が自己判断で欠勤し、会社が通常どおり業務を行っている場合などには、欠勤や有給扱いとなる可能性があります。事前に会社の規定や連絡体制を確認しておくことが重要です。いずれにしても、台風による休みに関して有給休暇の扱いをどうするかは、企業側の配慮と従業員との適切なコミュニケーションが不可欠です。
【従業員側】災害時の出社判断基準
会社側が全従業員に向けて自宅待機命令を出す場合もありますが、「各人の判断に任せる」と指示することもあります。この場合は、従業員それぞれが自分の置かれている状況を考慮しながら判断しましょう。ここでは、2つの状況パターンを例に挙げて解説します。
パターン1.きわめて危険性が高い状況
首都圏で台風や大地震などの災害が発生した場合、様々なトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
- 津波や洪水、浸水などの水害
- 火災などの二次災害に巻き込まれる
- 倒壊した建築物に挟まれる
- 割れた窓ガラスや看板が降ってくる
上記は災害時によくあるトラブルの例ですが、命に危険が及ぶものばかりです。危険と判断したら、たとえ出社命令が出たとしても応じる必要はありません。この様な危険な状況下では、「安全配慮義務」に違反するとして出社命令を出した企業側に責任が問われます。身の安全の確保を第一に、各自治体の指示に従って行動してください。
パターン2.出社が事実上不可能な状況
公共交通機関の計画運休など、出社が事実上不可能な場合があります。この場合判断基準は企業によって異なるため、従業員一人ひとりの判断に委ねられます。出社命令が出た場合は、企業側に違法性がないかどうかで判断することがポイントです。
事実上出社が不可能な状況で、「どんな手段を用いても出社せよ」と強要された場合は、違法性が高いため命令に従う必要はないといえます。出社が不可能な場合は、それぞれの状況に応じて以下の様な対応をしましょう。
- 途中帰宅
- 自宅待機
- 有給休暇の取得
- 欠勤
災害の規模にもよりますが、通勤中に災害に遭った場合は、途中で自宅に引き返すのが適切な対応といえます。交通ダイヤの乱れや駅での混雑が予想されるため、出社できない可能性があります。出社前であれば、自宅待機か有給休暇の取得、欠勤のいずれかで対応しましょう。災害の規模が小さければ、すぐに状況が改善され出社できることもあるため、会社に連絡を入れたうえで自宅待機をするのがおすすめです。
BCP対策としての電話代行の活用
地震や台風などの自然災害が発生すると、企業は通常業務の継続が困難になるケースも少なくありません。こうした非常時でも、取引先や顧客との連絡手段を確保し、従業員の安全を守るための体制づくりが求められます。BCP(事業継続計画)の一環として注目されているのが「電話代行サービス」の導入です。ここでは、災害時における電話代行の主なメリットをご紹介します。
※事業継続計画(BCP)は、会社が緊急事態に見舞われた時に、できるだけ以前と変わらず事業を継続するための計画です。
【関連記事はこちら】
>>事業継続計画(BCP)とは?策定方法を知ろう
①災害発生時の回線混雑リスクを回避できる
台風や地震などの自然災害が発生すると、電話回線が一時的に混雑し、外部との連絡が取りづらくなることがあります。こうした状況下で、企業の代表電話が機能しないと、取引先や顧客からの重要な連絡を受け損ねる可能性があります。電話代行サービスを導入しておけば、混雑による連絡遅延や情報漏れのリスクを軽減し、非常時にも確実に応対できる体制の構築が可能です。
②対外的な窓口業務を維持できる
災害によって営業停止やオフィスの閉鎖を余儀なくされた場合でも、電話代行サービスを利用すれば、対外的な窓口機能を維持できます。顧客や取引先からの問い合わせに対応することで、企業としての信用を損なわず、事業の継続性を担保することが可能です。
③従業員の緊急連絡・安否確認に対応
災害発生時には、従業員との連絡手段も混乱しがちです。従業員の安全確保や初動対応を、スムーズに進められるような体制を整えておく必要があります。電話代行を通じることで、従業員からの緊急連絡や安否報告を受け付け、その情報を社内の安否確認担当者へ迅速に共有できます。
自然災害は予期せぬタイミングで発生し、企業活動に大きな影響を及ぼします。従業員の安全確保はもちろん、外部との連絡手段の確保や情報伝達体制の維持は、企業としての信頼を守るうえでも非常に重要です。BCP対策の一環として「電話代行サービス」の導入は有効な手段といえるでしょう。
弊社、電話代行サービス株式会社では、災害時でも確実な電話応対体制を構築できるプランを提供しています。取引先や顧客からの問い合わせ対応はもちろん、従業員の緊急連絡・安否確認にも柔軟に対応可能です。企業の危機管理体制を強化するうえで、心強いパートナーとなるでしょう。災害時のリスクに備えるためにも、電話代行サービスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
【関連記事はこちら】
>>BCP対策の連絡手段に電話代行を活用!
最新記事 by 電話代行サービス株式会社広報部 (全て見る)
- 【シーン別例文付き】電話対応の敬語使い方完全ガイド - 2026年2月6日
- 個人タクシーに電話代行は必要?予約取りこぼし対策術 - 2026年2月4日
- 不明着信は出るべき?機会損失を防ぐ電話代行の効果 - 2026年1月30日







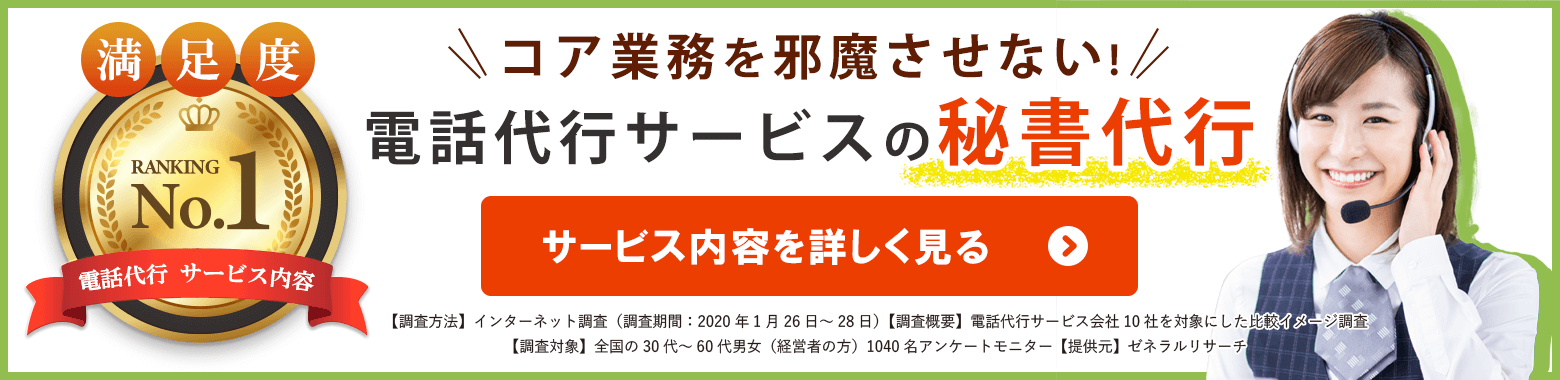

 【例文付き】謝罪訪問のアポの取り方やメールでの謝罪マナーを解説
【例文付き】謝罪訪問のアポの取り方やメールでの謝罪マナーを解説 新幹線のマナーを知ろう!電話はOK?上座はどこ?
新幹線のマナーを知ろう!電話はOK?上座はどこ? 顧客満足度を上げる行動とは?接客で大事な5つの”心がけ”
顧客満足度を上げる行動とは?接客で大事な5つの”心がけ” 落ち着いて対応しよう!電話メモの取り方のコツ
落ち着いて対応しよう!電話メモの取り方のコツ 【例文付き】社会人なら出来て当たり前!折り返し電話のマナー
【例文付き】社会人なら出来て当たり前!折り返し電話のマナー 代表電話は誰が出る?社内の電話番の重要性
代表電話は誰が出る?社内の電話番の重要性