弁護士は、弁理士や税務士の事務もできる?
更新日:2022.03.23 / 公開日:2017.04.25スタッフブログ
訴訟の代理や民事紛争の仲介など、弁護士は法律に関するさまざまな業務を取り扱います。「法律のプロ」として認知されている弁護士ですが、税理士や弁理士の事務行為もカバーできることはあまり知られていません。今回は、税理士や弁理士の事務を弁護士の職権として認める弁護士法3条2項についてご説明します。
弁護士は弁理士、税務士の仕事を兼務できる?
弁護士法3条2項について
まず、弁護士法3条には何と書かれているか、引用してみます。
弁護士法3条2項(弁護士の報酬)
弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
この様に、かなりはっきりと明記されています。つまり、弁護士であれば、税理士や弁理士の資格がなくても、それらの事務行為を担当することが可能というわけです。兼務できるということです。
ちなみに弁理士の事務内容は弁理士法4条に、税理士の事務内容は税理士法2条に定められています。
税理士の主な業務
- 確定申告に関する代理行為
- 税務に関する相談
- 税務署に提出する書類の作成
- 会計帳簿など財務書類の作成
弁理士の主な業務
- 特許や意匠、商標などの出願・登録に関する手続き
- 知的財産を巡る事案の仲裁処理
- 特許や著作権、ライセンスなどの契約交渉の代理
- 特許訴訟に関する訴訟代理
これらの業務もまた、弁護士が取り扱える内容です。
実際には、税理士や弁理士と連携して行う
法律的に、弁護士には税理士や弁理士の事務業務が担当できるといえ、専門性の高い事務処理に関しては税理士や弁理士と連携・協力しながら担当することがほとんどです。そのほうが依頼者にとっても安心で、よりスピーディな物事の解決が期待できるでしょう。
信頼できる弁護士が身近にいれば、税務や特許に関する代理行為を相談してみるのもいいかもしれません。弁護士を通じていい税理士や弁理士が見つかることも考えられますし、異なる士業の協同作業や連携プレーでベストな解決に結びつく可能性も期待できます。
とはいえ、「餅は餅屋」ということわざもあります。
あらゆる問題解決は、その道のプロに任せたほうが確実性は高いのも事実。いずれにせよ、ケースバイケースで、法律の便利な面を上手く活用したいですね。
The following two tabs change content below.


電話代行サービス株式会社は、東京・大阪に拠点を置く電話代行・コールセンター代行等の電話関連のBPOサービスを提供する会社。導入実績は全国で9,500社以上(2025年10月現在)。24時間365日対応可能で電話番号の貸出やチャット・SMSによる受電報告など、現代の業務スタイルに即した機能も充実。全国対応可能で、多様な業種への実績を持ち、企業の規模や課題に応じて最適な電話応対を設計・運用。人手不足や業務効率化にお悩みの企業様に、パートナーとしてご活用いただいています。
電話代行ビジネスインフォメーションでは、電話応対のアウトソーシングを検討している方向けに、電話代行や関連するビジネス情報を発信していきます。
電話代行について相談する
最新記事 by 電話代行サービス株式会社広報部 (全て見る)
- 作業中・夜間の電話取り逃しを防ぐ!カギ交換特化の24時間電話代行とは - 2026年1月14日
- 詐欺電話(なりすまし/迷惑電話)から会社を守る!電話代行活用術 - 2026年1月12日
- 接客中の電話、どうしてる?店舗の売上を守る“電話対応”の考え方 - 2026年1月9日


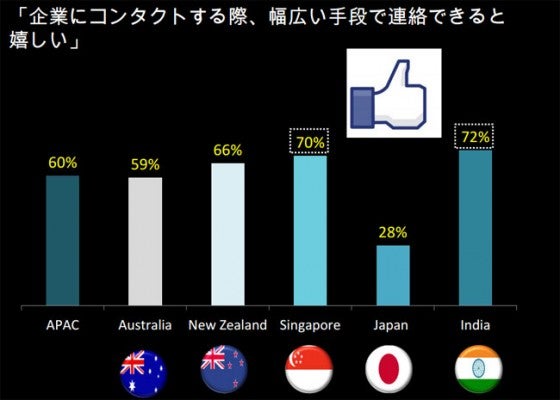 スマートフォンの普及率から見られる国別の差異
スマートフォンの普及率から見られる国別の差異 社会保険の対象者が増える!企業の注意点は?
社会保険の対象者が増える!企業の注意点は? ESG経営に企業が取り組むメリットと問題点
ESG経営に企業が取り組むメリットと問題点 5類移行で脱マスク!ノーマスクの生活マナーとは
5類移行で脱マスク!ノーマスクの生活マナーとは 電気代高騰!暖房器具の選び方やポイント
電気代高騰!暖房器具の選び方やポイント 建築士のキャリア|試験概要や資格取得後の流れ
建築士のキャリア|試験概要や資格取得後の流れ