部下が育つ「ほうれんそう」や「かくれんぼう」の重要性
更新日:2025.11.13 / 公開日:2019.11.28ビジネス豆知識ホウレンソウは、ビジネスシーンでは長い間部下を育てるうえで重要なコミュニケーション方法と認識されています。ただし、問題点も皆無ではなく、ビジネスの場では時代遅れとの声も聞かれます。そのような状況のなか近年は、「かくれんぼう」など、ホウレンソウに代わる新しいスキームが登場し始めました。この機会に、それぞれの意味や目的を確認しておけば、仕事に活かせるでしょう。そこで今回は、ホウレンソウ・かくれんぼうについて解説し、野菜で例える新しいコミュニケーション方法の意味・目的などをご紹介します。
【関連記事はこちら】
>>コミュニケーションを円滑にする方法
目次
ほうれんそう(報連相)は時代遅れ?
ホウレンソウは、ビジネスを円滑に進めるうえで必須とされる3つの要素(報連相)を端的に表した言葉です。ただし昨今は、報連相が古いとの声も聞かれます。
ホウレンソウの意味
ビジネスで用いられるホウレンソウの意味は、改めて示すと次の通りです。
・ホウ:報告(部下から上司への業務経過に関する報告)
・レン:連絡(仕事の当事者から関係者に向けた業務状況の連絡)
・ソウ:相談(自分が仕事で迷った時に上司の意見を聞く相談)
いずれも、仕事を進めるうえで誰もが心がけたい重要な作業であり、各々の頭文字を組み合わせてホウレンソウ(報連相)と呼ばれています。
報告の目的
ホウレンソウにおける報告の主な目的は、上司にかかる管理コストの削減です。部下が、自分の担当業務について適切に報告した場合、上司が疑問点や不明点を質問する時間は減らせるでしょう。具体的に経過報告が望まれる項目は、業務の進捗・仕事の成果や作業フローの変更点です。業務中にミスが見つかった時も、速やかに報告して指示を仰ぐと、問題の拡大防止や早期解決につながります。
自分のミスで上司や勤務先に余計な迷惑をかけないためにも、迅速・的確な業務報告は不可欠といえるでしょう。なお、上司への報告が必要となる場面としては、ミスが発覚した時のほか、クレームを受けた際やプロジェクトが途中になっている場合も挙げられます。
連絡の目的
ホウレンソウのうち連絡は、当事者自身と関係者との情報共有が主な目的です。ビジネスの場で仕事を進める時、会議の時間・場所やプロジェクトの変更点について必要な情報は、関係者に周知する必要があります。上司や部下にとどまらず、関係部署まで含めてチーム全体に連絡することが求められます。
その際、情報が行き渡らず関係者によって認識が食い違うと、チーム内で混乱が生じるかもしれません。混乱の収拾には時間がかかり、お互いの信頼関係を損ねる可能性もあります。時間の無駄遣いや信頼感の喪失は好ましくなく、業務状況の連絡は、客観的な情報を正確に伝えることが大切です。なお、関係者全体への連絡が必要な場面は、会議の時間・場所が変わった時や何らかの事情で作業に変更が生じた場合といわれています。
相談の目的
ホウレンソウの相談で重要な目的は、自分の手に負えない問題の早期解決です。仕事内容は必ずしも一様でなく、すべて自分1人で最後まで適切に処理できるとは限りません。自分の手に負えず判断に迷った時は、上司をはじめ周りの助言やサポートが必要になってきます。担当者としての責任感から何も相談せず無理に仕事を進めると、ミスの発生や納期の遅れにつながるケースが見られます。これらのトラブルを避けるなら、周りに相談しない姿勢は、得策とはいえないでしょう。
仕事をスムーズに進めるなら、自分の悩みや考えについて相談し、周りに意見を求めて問題解決に活かすことは大切です。なお、周りへの相談が望まれる場面には、担当したプロジェクトが滞った時や十分な成果が上がらず解決策も見つからない状況が挙げられます。ホウレンソウの意味や目的をふまえた場合、現在もビジネスにおける重要性は高いと考えられるため、簡単に時代遅れとはいえないでしょう。ただし、問題点がないわけではなく、仕事に取り入れる時は注意する必要があるとも指摘されています。
かくれんぼう(確連報)とは何か?
「かくれんぼう」は、ホウレンソウが抱える問題点を克服する目的で考案されたといわれるコミュケーション方法です。
ホウレンソウの問題点
ホウレンソウは、ビジネスの場で実践する時、「ソウ:相談」を中心に問題視されました。本来、「自分が判断に迷った時は相談して指示を仰ぐ」との意味を有していましたが、「相談すれば自分で悩まずに済む」といった姿勢が懸念されたためです。部下が仕事で困った時、安易に上司へ相談する意識が強まると、独力では何も考えない事態が生じると指摘されました。仕事の判断が他人頼みになり、自分で試行錯誤しなくなれば、さまざまな業務を経験するなかでの自立は難しくなるでしょう。
この問題をふまえ、部下の自立を促す必要から注目された方法が、「かくれんぼう」です。大きな特徴としては、ホウレンソウの「ソウ」から「カク」に変更された点が挙げられます。
かくれんぼうの意味
かくれんぼうの「れん」「ぼう」は、ホウレンソウの「ホウ」「レン」を継承し、それぞれ「連絡」と「報告」を意味しています。一方、「ソウ:相談」は消え、それに代わり新しく「カク:確認」が追加されました。「カク:確認」には、あらかじめ部下が自分の考えや提案を用意し、上司に確認してもらうとの意味合いが含まれています。
この場合、仕事で困った時も安易に相談できず、どのように対処するかの判断は周りに委ねられません。部下は、上司の判断・指示を求める前に、ある程度まで自分で思案する必要が出てきます。まず、自主的に考えてから上司に確認する姿勢が育まれると見込まれ、ビジネスの場で推奨されるケースは増えてきました。このように、かくれんぼうはホウレンソウの問題を改善した方法であり、その発展形ともいわれています。
【関連記事はこちら】
>>上手な部下の叱り方
野菜で例える新しいコミュニケーション
最近は、野菜で例える新しいコミュニケーション方法のアイデアが多彩です。具体的には、「ザッソウ・おひたし・こまつな・ちんげんさい」などが挙げられます。
ザッソウ
「ザッソウ」は、職場内で誰もが話しやすい環境づくりを目指す考え方です。この言葉の由来である雑草は、定義が明確ではないものの、一般には「雑多に生える草」の総称ともいわれています。一方、ビジネス用語の場合、「ザッ(ザツ)」は雑談・「ソウ」は相談を指しています。
また、ザッソウの主な目的は、雑談+相談を通して上司や部下とのコミュニケーションが取りやすい職場環境を整えることです。お互いに幅広いテーマで雑談・相談しながら、業務関係の報告・連絡が行いやすい雰囲気の形成を目指します。昨今は、ビジネスが多様化している影響でホウレンソウを守るのが難しくなりました。そのため業務報告や連絡作業を円滑化する目的で、ザッソウ(雑談・相談)を社内で採用する企業は増え始めたと見られています。
おひたし
「おひたし」は、人間関係や業務効率の改善を主目的とするコミュニケーション手法です。もともと、おひたしは野菜を出汁に浸す調理法ですが、ビジネスの場では違う意味でも使われています。それぞれの具体的な意味は、「お」:怒らない・「ひ」:否定しない・「た」:助ける・「し」:指示する、です。この使い方は、SNSの投稿に由来するといわれています。投稿者は、部下が適切にホウレンソウを実践できない原因が上司の態度にあると考えました。そのため、業務報告や連絡・相談を受ける時は「お・ひ・た・し」の4つを心がけていると説明しています。
上司がおひたしを意識した場合、部下のホウレンソウに対する不安は薄れるとの見方が有力です。結果的に、お互いがコミュニケーションを取りやすくなれば、良好な人間関係の構築や業務効率化につながると理解されています。
こまつな
「こまつな」は、基本的に業務の効率化を目指す仕事の進め方です。そもそも、語源である小松菜は、冬場が旬となる緑黄色野菜の1種です。最近は、部下が自分の手に負えない仕事を任された時、速やかに問題解決する対処法としても用いられています。ビジネス用語の意味を示すと、「こま」:困ったら・「つ」:使える人(できる人)に・「な」:投げる(協力を求める)です。
自分が苦手な業務を引き受けた際、1人で抱え込まず得意な人の協力を得れば、早期解決につながると説明されています。若手の従業員は、まだ力不足でも、仕事への責任感から無理するかもしれません。その際、この手法は、周りのサポートにより業務を効率よく進めるのに役立つとの声が多く聞かれます。
ちんげんさい
「ちんげんさい」は、上司が注意したい部下の状態を指した表現です。野菜のチンゲンサイは、春・秋の頃に旬を迎えるハクサイの仲間を指します。それに対し、ビジネス用語の意味合いは部下が発する危険信号であり、上司は異変のサインが見られないか日頃から気をつける必要があるといわれています。それぞれの言葉が意味する状態は、「ちん」:沈黙する・「げん」:限界までいわない・「さい」:最後まで我慢の3つです。
これらの信号を部下が発している場合、何か発言するたびに全否定されている恐れがあると指摘されています。部下が仕事で発言しにくくなり沈黙・我慢する状況は、ホウレンソウに差し支えるだけでなく、心身の不調も心配されるため見過ごせません。いずれも放置できない問題であり、上司は部下が気持ちよく働けるように配慮することが求められています。
以上の新しい方法や考え方は、それぞれ話しやすい環境づくり・人間関係の改善・業務効率化や部下のリスク回避に効果的です。そのため、ビジネスの場で導入するケースは、増えつつあると見られています。なお、ホウレンソウ・かくれんぼうやザッソウについて、言葉の意味や主目的をまとめると次表の通りです。
| 名称 | 言葉の意味 | 主な目的 |
|---|---|---|
| ホウレンソウ | 報告・連絡・相談 | 社内での情報共有 |
| かくれんぼう | 確認・連絡・報告 | 自立した人材の育成 |
| ザッソウ | 雑談・相談 | 話しやすい場の形成 |
| おひたし | 怒らない・否定しない・助ける・指示する | 人間関係の改善 |
| こまつな | 困ったら・使える人に・投げる | 業務の効率化 |
| ちんげんさい | 沈黙する・限界までいわない・最後まで我慢 | 部下のリスク回避 |
上記の方法を企業で取り入れる際は、適切に活用するため、各々の意味する内容とともに主な目的も把握しておくとよいでしょう。
進化するコミュニケーション・スキーム
ビジネスの場で用いられるコミュニケーション方法は、長年にわたり進化を続けているといえるスキームです。この点は、ホウレンソウからかくれんぼうへの変化を見ても理解できるでしょう。ホウレンソウは、現在のビジネスにも使える有用な手法ですが、時代が移り変わるなか主にソウの部分で問題が出てきました。近年は、ホウレンソウの問題点などを解消するため、かくれんぼうを含めた新しい手法が考え出されています。
今後も、これまでと同じく、ビジネスの場でコミュニケーション・スキームの改善は続くと予想されます。ただし、何の問題や欠点もない完璧なスキームの考案は、難しいかもしれません。このような状況を考慮した場合、各スキームの目的をふまえ、利用状況に応じて適切に使い分けることは大事です。ホウレンソウも、時代遅れと除外せず、現在のニーズに合わせて目的や手段を進化させる必要があると考えられます。
以上のように、既存・新規のコミュニケーション・スキームは、それぞれの特性を活かしながら効果的に活用するのが得策といえるでしょう。
【関連記事はこちら】
>>コミュニケーションがスムーズにいくメラビアンの法則とは
最新記事 by 電話代行サービス株式会社広報部 (全て見る)
- 電話代行でCL(顧客ロイヤリティ)改善へ~一次応答体制の作り方~ - 2026年1月23日
- ら抜き言葉・い抜き言葉とは?意味と違いをわかりやすく解説 - 2026年1月21日
- 作業中・夜間の電話取り逃しを防ぐ!カギ交換特化の24時間電話代行とは - 2026年1月14日

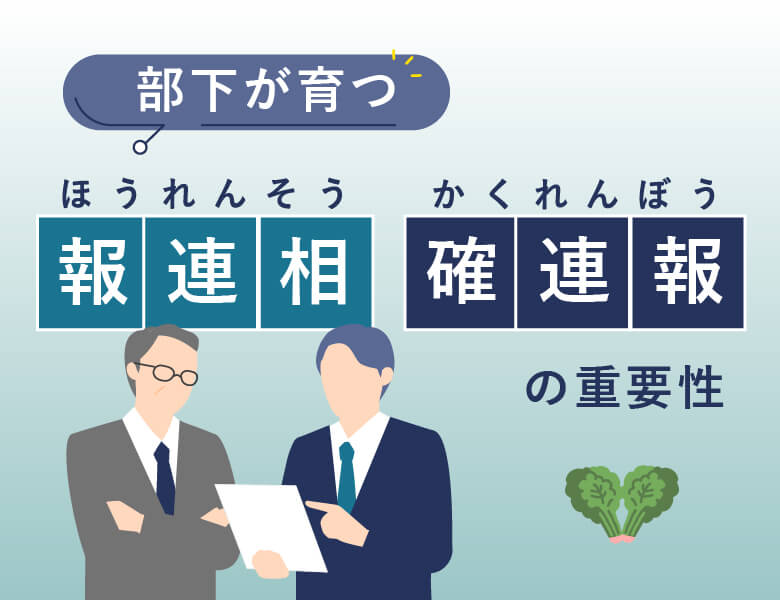

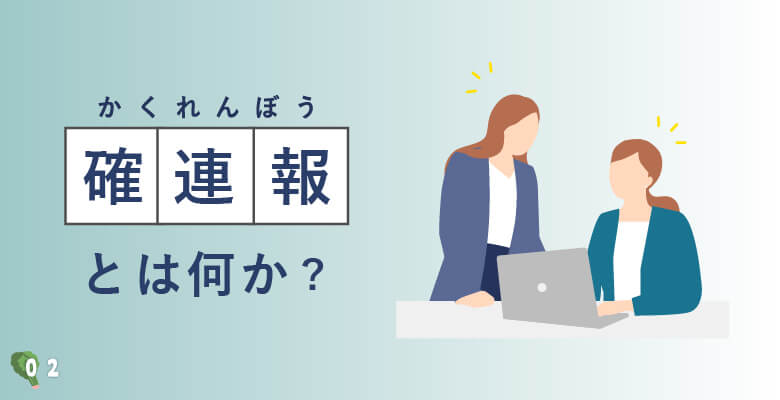
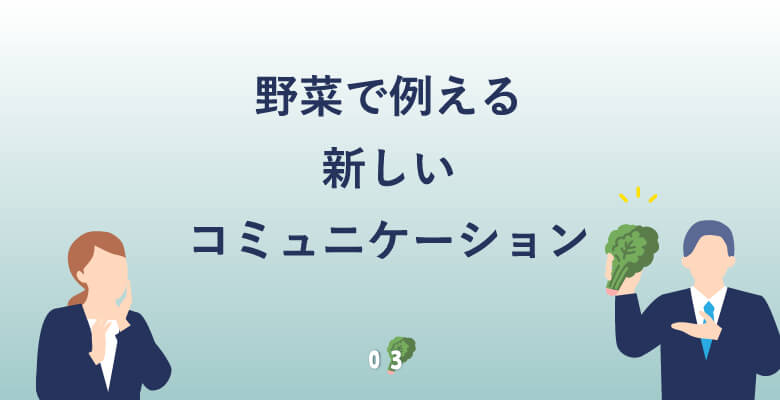
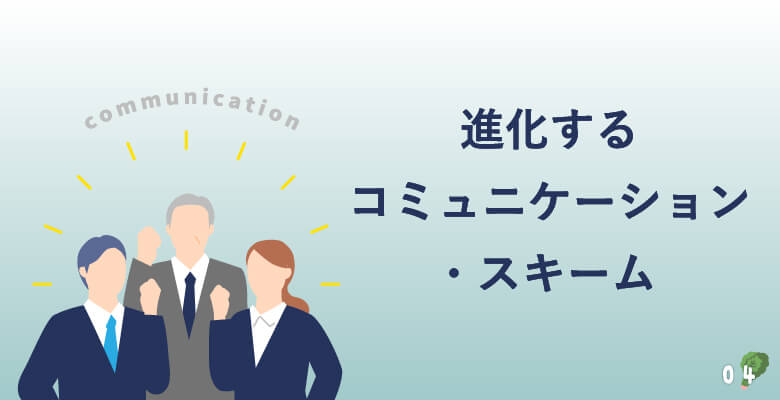

 シニアの士業独立はあり?老後を専門資格で生き抜く
シニアの士業独立はあり?老後を専門資格で生き抜く ビジネスマン必見!読書術をアップする方法
ビジネスマン必見!読書術をアップする方法 ケイパビリティとは
ケイパビリティとは オンボーディングとは
オンボーディングとは 意外と知らない社長の仕事!
意外と知らない社長の仕事! オンライン商談や会議での資料作成のコツ
オンライン商談や会議での資料作成のコツ